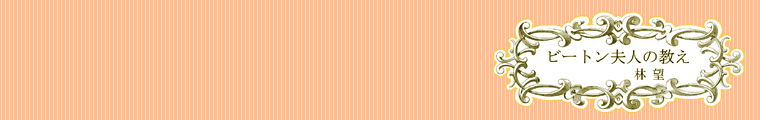ビートン夫人の教え
2 家庭の原理原則 <前編>
なにしろしかし、ビートン夫人は十九世紀の人であったことは動かない事実なのであって、過剰に近代的な思想を期待することは本来間違っている。だれだって(よほどな天才でもないかぎり)その時代の風潮というものから完全に自由ではありえないのだ。
ただ、面白いことは、彼女が生きていた時代というのは、イギリスにおける一種の啓蒙時代であって、あたらしく確立し勢力を持つに到った新興中産階級の人々の間で、生活規範や道徳、あるいはもう少しひろくは人生論のようなものがもてはやされた時代だったということである。
そのため、この「家事の教科書」にはさまざまの教訓的引用などが鏤められ、あたかもそれは料理の本というよりは、むしろ家庭における実践倫理の書であるような相貌をさえ垣間見せる。
しかし、その一見旧弊に見える教訓のなかにも、今日の私たちが再評価しなくてはいけない生活道徳のようなものが現れてくることに注目してみたいのである。
まずビートン夫人は、こういうことを言っている。ただし、これは十九世紀的中産階級の家の女主人の心構えを説く冒頭の一節で、現代の「主婦」という立場とはちょっと違っていることに留意して読まなくてはならない。そこにはメイドや料理人など、何人かの使用人の存在が前提されているからである。
「一家の女主人は一軍の将、あるいは企業の統率者にも譬えられましょう。女主人の精神は家全体に表れるもので、女主人が、知性をもって、その任をきちんと遂行するならば、使用人たちは自ずからそれを模範とするに違いありません。思うに、女性の特質として具わったものの中で、およそ家事の仕事についての知識以上のものはないのです。家族の幸福、安心感、そして健康は、あげてここにかかっています」
とこう述べたあとで、オリヴァー・ゴールドスミスの『ウェィクフィールドの牧師』(1766年刊)を引用して、己の意見の補強を試みたりする、とそういうところが、単なる料理家ではなくて、フランス文学の翻訳などにも手を染めた智識人としてのイザベラ・ビートンの面目躍如たるところである。曰く、
「謹み深き乙女、賢明なる妻、注意深き夫人は、ペチコートをはいた哲学者や、怒鳴り散らす女傑や、口やかましい女王なんぞよりも、人生においてはるかに役に立つというものだ。夫や子供を幸せにできる女、悪から人を立ち直らせたり、人を善行に導くような女は、ロマンス小説でおなじみの、矢筒や目から放つ矢で人を殺すことに専念しているご婦人方より遥かに遥かに偉大である」
つまり、こういうところを読んでみると、この当時、だんだんと人権意識に目覚めた女性たちが、いわゆる女権拡張運動などを起しつつあったイギリスの、ある種独特の空気が感じ取れる。
ビートン夫人は、しかし、そういう運動には寧ろ後ろ向きで、家庭に関しては保守的な志向を持っていた人である。
けれどもそれは、反動的であったというよりは、そういう穏健な生き方のほうが実際に多くの人を幸福にする、と考えていた彼女の正直な思いの発露なのであろうと私は想像する。なにせ、彼女は当時まだ二十代で、若くてナイーブで、そして家庭的に充分幸せなる妻であり母だったのだ。
二十一世紀の現代、今や働く女性という「人生の形」は当たり前となって、次第に「専業主婦」のような生き方は衰微に赴きつつあるけれども、はたしてそれだけが本当に人生の幸福であるのかということについては、そろそろ再評価の時期がきているように思われる。
もし善良で真面目な、そして家庭にも充分の愛情を注ぐような尊敬すべき夫に恵まれるならば、女性の生き方として、家庭のなかで穏やかに家事や子育てに専念するというのも、必ずしも悪いものではあるまい。
現代の働く女性たちのなかには、家庭に専念するいわゆる専業主婦を指して、あたかも卑怯者のように非難する人もあるけれど、私はそういう考えに与しない。
外でバリバリと働くのも人生なら、家庭で真摯にしかし楽しく子育てをして、穏健な暮しに知足安分するのもまた立派な人生だと私は信ずる。自己実現の仕方は、人により、志向により、けっして一様ではないのである。
しこうして、ひところのような激しいフェミニズムは反省されて、やはり(とりわけて日本では)男女は調和して協同しつつ、或る程度の任務を分け合って暮らすということが再評価されつつあるのが現代という時代であろうと思われる。かかる時代に向き合ってみると、この十九世紀的な観念のなかに、一面の真理があるように見えてくる。
この後で、夫人は筆をついで次のように述べる。
「ひとこと付言するならば、よい主婦になるについては、決して正しい娯楽や面白い気晴らしを諦めるには及びません。女主人としての職務を全うすることと、人生を楽しむ事は両立できないと思い込んでいる向きもあるかもしれないので、今ここに、そうではないのだということを、特に記しておかなくてはなりません」
イザベラ・ビートンの思考傾向は、あまり宗教的ではない。むしろ、この本の全体を通して、キリスト教的なドグマは決して表面だって強調されることはなく、むしろ一人一人の市民が、一個独立の個人として、自助自立の精神を持つべきことが基本的な考え方のように思える。
それは、かのサミュエル・スマイルズの『セルフ・ヘルプ』にも通じる考え方で、この比較的稀薄な宗教性と、より強固な自立性が、十九世紀の世界帝国イギリスを支えてきた力であったことを想起する必要がある。
つまり、そういう意味で、イザベラは確かに典型的にヴィクトリア時代の女性であったのである。
したがって、彼女が強調している徳目・・・というか家庭を経営していくのに必須の心がけ、とでもいうべきものは、すぐれてヴィクトリア時代風である。
すなわち、まず第一に、「早起きの徳」ということを説いている。
これは一つにはそれが健康の元であるということ、そしてそれ以上に大事なことは、主人が早寝早起きの習慣を身に付けている場合、使用人たちもまた、等しく早寝早起きをしなくてはならないことになるからである。それは使用人たちの夜更かしによる自堕落を防止するのに必要な要件だ、というのである。こういうところにもまた、ビートン夫人は、ちゃんと偉人の箴言を鏤めておくことを忘れなかった。ここでは、大チャタム卿(初代チャタム伯爵ウイリアム・ピット’The Elder’、1708-78)の言葉を引用してみせる。曰く、
「ベッドのカーテンや部屋の壁など、到るところに『朝早きに起きざれば、日に何事も為しえず』とでも書きつけておくがよろしい」
と。こういう露骨な教訓性は、現代から見るとなんだかすこしウルサイような気がするかもしれないが、当時の人たちにとっては、こうした教訓を知り、之を拳々服膺することで自分が少し偉くなったような気持ちを持つことができて、これはまことに興味深く有益な書物であるという感想を持ったことであろう。
かかる教養主義的傾向は、この本がもつ顕著な特色であって、当時の人たちがどんな生活意識をもって暮らしていたかということを知る良い材料でもある。おそらくは、こんなところを読んでベッドのカーテンに『朝早きに起きざれば、日に何事も為しえず』と麗々大書して家族を閉口させたおかみさんなども必ずやいたことであろうと想像することができる。
そういえば、かつて私が下宿していたルーシー・ボストン夫人の領主館の梁には「VOCATUS ATQUE NON VOCATUS DEUS ADEST」(呼ぼうと呼ぶまいと、神はここにまします)と彫りつけてあったし、また、オクスフォードのイフリーにある「旧牧師館」というランドマークトラストの持ち物の館(15世紀の建築)の居間の壁間には「もしこの現世の家の破却さるとも、なお我らには神の家居あるを知るべし。そは人の手もて造れるものにあらず。天上の永久の家なり」というような意味のラテン語の箴言(おそらくは十九世紀の装飾)が欄間あたりにぐるりと書かれていた。
かかる実例を想起するとき、このビートン夫人が紹介したような徳目をば、ほんとうにカーテンや壁に書いて日々眺めていた人がきっと居ただろうと、どうしても想像せずにはいられない。実は、イギリス人は案外と標語好きなのである。ただ、ヴィクトリア時代の新婦人であったイザベラは、神への帰依の代わりに市民的勤勉を標語として掲げたというところであった。
次に夫人は、「清潔さ」をば、健康に不可欠なものだとして強調し、そのために家の構造やインテリアについて学ぶことを勧めている。しかも、(これはイギリス人としては異例であるが)「毎朝、水あるいはぬるま湯で入浴すべきこと」を教えている。
現在だってイギリス人は毎日風呂になど入らない人が少なからぬことを思うと、衛生観念の稀薄であった当時にあっては、毎日風呂を使えなどというのは、じっさいかなり破天荒なる言い草であった。
それどころか、あまり風呂になど入り過ぎると病気になるもとだ、などということをまことしやかに言うイギリス人は現在でも確実にいるのである。それを思うと、まだ衛生学なども充分発達していなかった当時にあって、これがすこぶる先鋭的な意見であったことは知っておくべきである。
(後編につづく)
ただ、面白いことは、彼女が生きていた時代というのは、イギリスにおける一種の啓蒙時代であって、あたらしく確立し勢力を持つに到った新興中産階級の人々の間で、生活規範や道徳、あるいはもう少しひろくは人生論のようなものがもてはやされた時代だったということである。
そのため、この「家事の教科書」にはさまざまの教訓的引用などが鏤められ、あたかもそれは料理の本というよりは、むしろ家庭における実践倫理の書であるような相貌をさえ垣間見せる。
しかし、その一見旧弊に見える教訓のなかにも、今日の私たちが再評価しなくてはいけない生活道徳のようなものが現れてくることに注目してみたいのである。
まずビートン夫人は、こういうことを言っている。ただし、これは十九世紀的中産階級の家の女主人の心構えを説く冒頭の一節で、現代の「主婦」という立場とはちょっと違っていることに留意して読まなくてはならない。そこにはメイドや料理人など、何人かの使用人の存在が前提されているからである。
「一家の女主人は一軍の将、あるいは企業の統率者にも譬えられましょう。女主人の精神は家全体に表れるもので、女主人が、知性をもって、その任をきちんと遂行するならば、使用人たちは自ずからそれを模範とするに違いありません。思うに、女性の特質として具わったものの中で、およそ家事の仕事についての知識以上のものはないのです。家族の幸福、安心感、そして健康は、あげてここにかかっています」
とこう述べたあとで、オリヴァー・ゴールドスミスの『ウェィクフィールドの牧師』(1766年刊)を引用して、己の意見の補強を試みたりする、とそういうところが、単なる料理家ではなくて、フランス文学の翻訳などにも手を染めた智識人としてのイザベラ・ビートンの面目躍如たるところである。曰く、
「謹み深き乙女、賢明なる妻、注意深き夫人は、ペチコートをはいた哲学者や、怒鳴り散らす女傑や、口やかましい女王なんぞよりも、人生においてはるかに役に立つというものだ。夫や子供を幸せにできる女、悪から人を立ち直らせたり、人を善行に導くような女は、ロマンス小説でおなじみの、矢筒や目から放つ矢で人を殺すことに専念しているご婦人方より遥かに遥かに偉大である」
つまり、こういうところを読んでみると、この当時、だんだんと人権意識に目覚めた女性たちが、いわゆる女権拡張運動などを起しつつあったイギリスの、ある種独特の空気が感じ取れる。
ビートン夫人は、しかし、そういう運動には寧ろ後ろ向きで、家庭に関しては保守的な志向を持っていた人である。
けれどもそれは、反動的であったというよりは、そういう穏健な生き方のほうが実際に多くの人を幸福にする、と考えていた彼女の正直な思いの発露なのであろうと私は想像する。なにせ、彼女は当時まだ二十代で、若くてナイーブで、そして家庭的に充分幸せなる妻であり母だったのだ。
二十一世紀の現代、今や働く女性という「人生の形」は当たり前となって、次第に「専業主婦」のような生き方は衰微に赴きつつあるけれども、はたしてそれだけが本当に人生の幸福であるのかということについては、そろそろ再評価の時期がきているように思われる。
もし善良で真面目な、そして家庭にも充分の愛情を注ぐような尊敬すべき夫に恵まれるならば、女性の生き方として、家庭のなかで穏やかに家事や子育てに専念するというのも、必ずしも悪いものではあるまい。
現代の働く女性たちのなかには、家庭に専念するいわゆる専業主婦を指して、あたかも卑怯者のように非難する人もあるけれど、私はそういう考えに与しない。
外でバリバリと働くのも人生なら、家庭で真摯にしかし楽しく子育てをして、穏健な暮しに知足安分するのもまた立派な人生だと私は信ずる。自己実現の仕方は、人により、志向により、けっして一様ではないのである。
しこうして、ひところのような激しいフェミニズムは反省されて、やはり(とりわけて日本では)男女は調和して協同しつつ、或る程度の任務を分け合って暮らすということが再評価されつつあるのが現代という時代であろうと思われる。かかる時代に向き合ってみると、この十九世紀的な観念のなかに、一面の真理があるように見えてくる。
この後で、夫人は筆をついで次のように述べる。
「ひとこと付言するならば、よい主婦になるについては、決して正しい娯楽や面白い気晴らしを諦めるには及びません。女主人としての職務を全うすることと、人生を楽しむ事は両立できないと思い込んでいる向きもあるかもしれないので、今ここに、そうではないのだということを、特に記しておかなくてはなりません」
イザベラ・ビートンの思考傾向は、あまり宗教的ではない。むしろ、この本の全体を通して、キリスト教的なドグマは決して表面だって強調されることはなく、むしろ一人一人の市民が、一個独立の個人として、自助自立の精神を持つべきことが基本的な考え方のように思える。
それは、かのサミュエル・スマイルズの『セルフ・ヘルプ』にも通じる考え方で、この比較的稀薄な宗教性と、より強固な自立性が、十九世紀の世界帝国イギリスを支えてきた力であったことを想起する必要がある。
つまり、そういう意味で、イザベラは確かに典型的にヴィクトリア時代の女性であったのである。
したがって、彼女が強調している徳目・・・というか家庭を経営していくのに必須の心がけ、とでもいうべきものは、すぐれてヴィクトリア時代風である。
すなわち、まず第一に、「早起きの徳」ということを説いている。
これは一つにはそれが健康の元であるということ、そしてそれ以上に大事なことは、主人が早寝早起きの習慣を身に付けている場合、使用人たちもまた、等しく早寝早起きをしなくてはならないことになるからである。それは使用人たちの夜更かしによる自堕落を防止するのに必要な要件だ、というのである。こういうところにもまた、ビートン夫人は、ちゃんと偉人の箴言を鏤めておくことを忘れなかった。ここでは、大チャタム卿(初代チャタム伯爵ウイリアム・ピット’The Elder’、1708-78)の言葉を引用してみせる。曰く、
「ベッドのカーテンや部屋の壁など、到るところに『朝早きに起きざれば、日に何事も為しえず』とでも書きつけておくがよろしい」
と。こういう露骨な教訓性は、現代から見るとなんだかすこしウルサイような気がするかもしれないが、当時の人たちにとっては、こうした教訓を知り、之を拳々服膺することで自分が少し偉くなったような気持ちを持つことができて、これはまことに興味深く有益な書物であるという感想を持ったことであろう。
かかる教養主義的傾向は、この本がもつ顕著な特色であって、当時の人たちがどんな生活意識をもって暮らしていたかということを知る良い材料でもある。おそらくは、こんなところを読んでベッドのカーテンに『朝早きに起きざれば、日に何事も為しえず』と麗々大書して家族を閉口させたおかみさんなども必ずやいたことであろうと想像することができる。
そういえば、かつて私が下宿していたルーシー・ボストン夫人の領主館の梁には「VOCATUS ATQUE NON VOCATUS DEUS ADEST」(呼ぼうと呼ぶまいと、神はここにまします)と彫りつけてあったし、また、オクスフォードのイフリーにある「旧牧師館」というランドマークトラストの持ち物の館(15世紀の建築)の居間の壁間には「もしこの現世の家の破却さるとも、なお我らには神の家居あるを知るべし。そは人の手もて造れるものにあらず。天上の永久の家なり」というような意味のラテン語の箴言(おそらくは十九世紀の装飾)が欄間あたりにぐるりと書かれていた。
かかる実例を想起するとき、このビートン夫人が紹介したような徳目をば、ほんとうにカーテンや壁に書いて日々眺めていた人がきっと居ただろうと、どうしても想像せずにはいられない。実は、イギリス人は案外と標語好きなのである。ただ、ヴィクトリア時代の新婦人であったイザベラは、神への帰依の代わりに市民的勤勉を標語として掲げたというところであった。
次に夫人は、「清潔さ」をば、健康に不可欠なものだとして強調し、そのために家の構造やインテリアについて学ぶことを勧めている。しかも、(これはイギリス人としては異例であるが)「毎朝、水あるいはぬるま湯で入浴すべきこと」を教えている。
現在だってイギリス人は毎日風呂になど入らない人が少なからぬことを思うと、衛生観念の稀薄であった当時にあっては、毎日風呂を使えなどというのは、じっさいかなり破天荒なる言い草であった。
それどころか、あまり風呂になど入り過ぎると病気になるもとだ、などということをまことしやかに言うイギリス人は現在でも確実にいるのである。それを思うと、まだ衛生学なども充分発達していなかった当時にあって、これがすこぶる先鋭的な意見であったことは知っておくべきである。
(後編につづく)