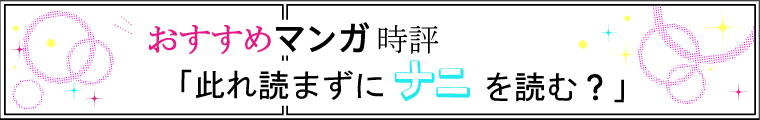おすすめマンガ時評『此れ読まずにナニを読む?』
第38回 『護法少女ソワカちゃん』 kihirohito
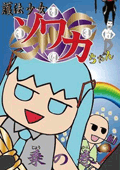
(C)kihirohito/Crypton Future Media Inc.
「“アーバンギャルド”(テクノポップ系のアンダーグラウンド・バンド)のCDの隣に置かれるべきじゃないですか」と言ってはみるけれど、実際には「蛙男商会」や「やわらか戦車」の隣に置かれるのが妥当なところだろう。
もともと動画共有サイト「ニコニコ動画」にアップされた動画である。作者はkihirohitoなる男性。「初音ミク」ほかのボーカロイド(サンプリングされた声優の声を用い、「歌わせる」ことのできるソフトウェア・シンセサイザー)を使って、「一人の少女が自らの冒険譚を歌って聞かせる」という「仏教系魔法少女モノ」だ。
だいいち、この連載は「おすすめのマンガ」を紹介するコラムだったはずだ。
そこでどうしてアニメの話をするのか、と思われることだろう。だが『ソワカちゃん』には、特異な「語り」の構造がある。またそこで「フキダシ」が使われていることから、一応「マンガ」との連なりでみることができる。
ぼくはこの一年半ほど、『ソワカちゃん』にはまり続けてきた。
『ソワカちゃん』は、アニメと言っても、動きは最小限。絵はいわゆるヘタウマ調、「ソワカちゃん」や「クーヤン」など、ユニークなキャラたちが繰り出す小ネタは、馬鹿馬鹿しかったりひねっていたりして笑えるというものだ。さらに、仏教、オカルト、ミステリ、ニューアカデミズム、現代美術といったネタが過剰なほどに引用される。それは、一見して言葉遊びや悪ふざけのように見えるが、どうやら結構まじめな教養に裏打ちされているようだ。
とはいっても、こうしたネタのマニアックさのせいか、熱狂的な人気に支えられてはいるものの、それは一部に限られるとみられてきた。実際、「ニコニコ動画」での動画再生数(のべ何人が過去に再生したかが表示される)も、最高で約17万(2009年7月8日現在)と、ボーカロイドを使ったオリジナル作品の最人気作と比べると、一桁少ない。
ところが、アマゾンでDVDの予約が始まってみると、「アニメ」のカテゴリで最高位5位を記録してしまった。これが瞬間のことならば、一部の熱心なファンが一斉に予約注文をした結果と解釈すれば済むのだが、そうでもない様子もある。そもそもまだ「ニコ動」以外に存在を知る回路には乏しい作品である。発売元の話だと、誰に売れているのか分からないのだという。
ぼく自身、『ソワカちゃん』は、楽曲のベースが1980年代ニューウェーヴ、それもアンダーグラウンドな方面にあることもあわせ、ファンの多くは自分と同じような1980年代サブカル親父が中心だとばかり思っていた。ところがそうではなく、10〜20代の女子がファンの中核をなしているようなのだ。昨夏参加したファン主催のトークイベントの客層もそうだったし、今年になってからは、学校で「先生、私ソワカちゃんのファンなんです」と言って話かけてくる学生にも出くわした。1980年代サブカルチャーの記憶など当然持っていない彼女らは、キャラの面白さから入っているようだった。
ネット発の、ことオタク系のコンテンツは、概してファン同士のコミュニティを母体に大きくなる。ここでいう「コミュニティ」とは、ファンが相互に、同じものを愛好していることを根拠に共感しうるという前提を共有する集団というほどの意味である。
そのため、それぞれのファンコミュニティの住人たちは、お互いに似たような趣味嗜好を持ち、ほかに愛好するアイテムもある程度似通ったものということを、ある程度前提にすることができた。「メカ」や「SF」が好きなオタク男子ならば、おおむね「美少女」も好きであろうという命題を、それ自体の実証は脇に置いたまま、とりあえず前提とできたのである。
ところが、ウェブの普及以降は、さまざまな趣味の多様性が可視化され、この前提はいよいよ通用しなくなったと思われる。そのことは、逆にコミュニティの様相も変えているように思える。『ソワカちゃん』ファンの多様性は、そのひとつのあらわれなのかもしれない。
たとえば、女子ファンたちが「腐女子」ばかりかといえばそうでもない(もちろん、腐女子のひともいる)、また、文芸よりの「小難しい話」を好むファンもいれば、そうでない人もいる。「『ソワカちゃん』ファンとはこういう人」とひとことで形容することは難しい。言い方を変えれば、像を結ばない。
おそらく、こうしたファンの多様化は、『ソワカちゃん』では多少際立っているのだろうけれど、けっして『ソワカちゃん』に固有なことではないだろう。
「ニコニコ動画」などの情報インフラや、「ボーカロイド」というものが、「歌」と「キャラ」の両面を持つことや、受け手の世代的な変化といった要素が重なり合っていると考えたほうが適切であるように思える。
しかし、ボーカロイドの「歌」と、歌詞(動画の上にも字幕を表示できる)と、作中のキャラとフキダシなどで添えられるセリフという異なる三層で「物語る」という形式が、ウェブと「ニコニコ動画」を基盤とした新しいものであることは間違いない。
マンガの「未来」を考えたとき、ウェブを軸にした新しい形式へと変貌を遂げる方向が強調されることがままあるが、そこでは、アニメやゲームなどと混淆した形態が想定されることがある。『ソワカちゃん』のような複雑な構造を持った「語り」は、その試行錯誤のひとつの形であろう。(伊藤剛)