おすすめマンガ時評『此れ読まずにナニを読む?』
第21回 『 NANA 』 矢沢あい (集英社)
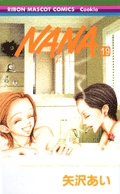
(C) 矢沢漫画制作所/集英社クッキー
平凡な家庭で育ち、特にやりたいこともない恋愛体質のふわふわした小松奈々(ハチ)と、幼い頃親に捨てられ、深く愛していた相手・レンと別れてまでバンドでの成功を目指す一見クールな大崎ナナ。対照的な同い年の二人の「ナナ」は、上京する新幹線の中で偶然出会い、やがて一緒に暮らし始める。なにからなにまで正反対、と言っていいこの二人を中心に物語は進行する。
それにしてもなぜ、『NANA』はこんなにヒットしたのだろう。ふだんマンガを読まないのに『NANA』だけは読む、という女子がたくさんいる、という話もよく耳にした。マンガをあまり読まない女子たちをも巻き込んで支持された理由。
それは、『NANA』の「リアルとファンタジーの、みごとなさじ加減」に秘密があるのではないか(ここでいうファンタジーとは「(女の子にとって)こうだったらいいな」、という夢、というような意味である)。
まず、絵柄。少女マンガの目はやたら大きくて目の中に星がまたたいている、と揶揄されるが、『NANA』における登場人物の目の大きさは、実際の人間の目の大きさや形に近く(ここがリアル)、でも「ちょっとだけ(少女マンガ的に)誇張」した描き方になっている(ここがファンタジー)。
ナナとハチの住む家賃7万円の多摩川沿いの古いアパートは、エレベーターがなくて(ここがリアル)、だけど作中の8畳のDKも6畳の自室もなんだかやけに広いし、バスタブはなんと猫足(ここがファンタジー)。
「ありえな〜い」「でもそうだったらいいな」というファンタジー要素と、「なんかホントっぽい」と感じるリアルの絶妙さ。もちろん私だって、ナナとハチの暮らす部屋に「8畳にしては広ッ!!」などとツッコみつつも「こんなカワイイ部屋、いいなぁ」とうっとりせずにはいられない。
CGで加工された現実にある(と思われる)風景を背景に、現実に存在するブランドの服をまとった、でもすごく細くてかっこいい(かわいい)登場人物たちが織りなす物語。それでいて、注意深く、リアルとファンタジーのチューニングがなされていることは、東京の地名は具体的に出てくるのに、ナナとハチの故郷の地名ははっきり明示されないところからもわかる。フツーなハチは「どこでもありうる地方都市」の出身で、それが多くの読者の共感を得る部分になっているのだろう。
そして、もっとも「矢沢あい、おそるべし」なところは、目もくらむような「ファンタジー要素」でコーティングしながら、現実的な容赦ない「リアル」を物語の中で見せていくところではないだろうか。
たとえば、「やさしい彼」は、心変わりをする優柔不断な彼でもあること。
「皆の憧れのアーティストの彼」は、同時に「社会で成功している冷徹なリアリスト」でもあり、「自分を組み敷く暴君」でもあること。
女の子である、ということは、一途な愛(のつもり)の結果でも、望まない妊娠する肉体をもっている、ということ。
そして、「なにより大切に思ってた女ともだち」との生活も、あっけなく崩れてしまいうること。
ふだんマンガを読まない女の子たちも、おしゃれな絵柄や目を離せないドラマ展開の底に流れる、その「リアル」さを「信頼」して、『NANA』を支持したのではないだろうか。
思えば私の小学生時代、愛読していた少女マンガ誌『りぼん』では、平凡な女の子が好きな男の子に「そのままの君が好きだよ」と言われてハッピーエンドをむかえる、「乙女ちっく」と呼ばれるマンガが大人気だった。それは、現実の恋愛そのものというよりは、「そうだったらいいな」という「女の子の夢」の物語だった。
私が読者を卒業した後の『りぼん』で長らく看板作家であった矢沢あいが、『りぼん』を離れ「少女むけ」という制約をはずして、男の子と女の子が結ばれてめでたしめでたし、の「先」を描いた物語、それが『NANA』だ。現実とつながりを感じさせつつも少女マンガ的な洗練をとげた絵柄で、とびきりの「夢」設定でコーティングしながら、「容赦ないリアル」を含みつつ、展開していく物語なのだ。
矢沢あいは、ヒット作『ご近所物語』や『Paradise Kiss』で、ずば抜けた才能をもった女の子が困難にめげず、夢をかなえるお話を描いてきた。だが、少女誌『りぼん』を離れ、ファッション誌『Zipper』で連載された『Paradise Kiss』のラストに萌芽が見えるように、どんなに願ってもかなわぬ夢もあるし、誰もが『ご近所…』のヒロイン実果子のようにクリエイターとして成功したり、『Paradise…』の紫のように恵まれた容姿でモデルに抜擢されるわけにはいかない。矢沢あいは、その残酷ですらある「リアル」から目をそらさずに、なおかつ多くの人を引きつける物語を紡ぐことができる強靱な作家なのだ。
正直に告白すると、私は長いこと『NANA』という作品がニガテだった。なんだか、登場人物、特に、ハチに対してうまく距離がとれなくて、「ハチよ、あなたの人生、男任せか。そんなことでいーのか」などと、まるで実在の友人にでも言うかのような言葉が胸をよぎりまくり、『NANA』というフィクションをうまく楽しめなかったのだ。もちろん、そもそもハチに実在の友人に対するようなツッコミをいれてしまうこと自体が、「強烈なリアリティ」を感じている、ということに他ならない。そう、リアルとファンタジーをたくみに操る「矢沢あいマジック」に翻弄されている証なのだ。
ナナもハチも作者が作った登場人物なのに、その弱さやダメさまでもがあまりに生々しいため、「なんだか本当にいる人」であるかのように無意識に読んでいた私だが、あるとき作家・中村うさぎ氏のこんな発言を読んで、見方が変わった。
小倉千加子氏との対談集『幸福論』(岩波書店)のなかで、中村氏は、ナナとハチは「ひとりの女の子の中の、ふたつの人格」の表現であると言う。中村氏の中ではずっと「ナナの私」と「ハチの私」が戦っていて、「私の世代(注:中村うさぎ氏は1958年生まれ)の不幸はナナとハチがずっとけんかし続けていたこと」だ、それが、このマンガの中で和解した、と言うのだ。
「バンド(仕事)で夢をかなえて自分の足で立つ」という社会的自己実現にこだわるナナと、「好きな人と結ばれて幸せになる」という性的自己実現を夢見るハチ。それは、女の人のなかにある二つの面を象徴していて、二人が仲良く暮らすことで「和解」したのだ、と。
なるほど。そういう見方をすれば、ナナとハチの二人が強くひかれあうこと、そして、どちらかだけだと「何かが欠落している」かのような喪失感に襲われることもうなづける。
長々と解釈を書いてきたけれど、単純に「お話」として読んでも、『NANA』は、未来から過去を回想する、という形式のナレーションを用いながら、その「未来」のドラマも進行しつつ、二つの時間軸が行き来する、という構造で、この先どうなるのだろう、という興味をかきたてるお話だ。
うーん。よくできている。私はもう一度つぶやいてしまう。矢沢あい、おそるべし。
ひねくれた読者である私はつい、ナナやハチに「お互いそんなにもたれあったら、破綻しちゃうよ」などと、ハチに説教する友人の淳子みたいなことを言いたくなっちゃうけれど、それでも。
それでもそういう「説教スイッチ」を切って物語を読むと、ハチの「誰かを愛したい、誰かに必要とされたい」というひたむきさと、一見強いナナの足下に広がるすさまじい孤独、そしてそれを慰めた「特別なにができるわけでもないハチ」の存在の意味と、「どんなに大事にしていたものでも、失ってしまうことがある」ことの切なさが、胸に迫ってくる。
矢沢あいという手練れの作家のマジックにまんまとハマって、たまに「でもやっぱハチってどうよ」「ナナ、大丈夫?」とかブツブツ言いながらも、完結をじりじりと待ってしまいそうなのだ。(川原和子)
