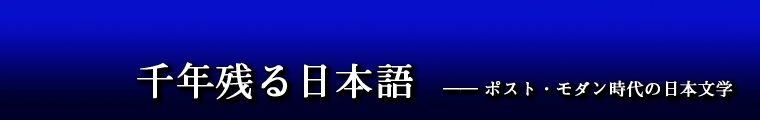千年残る日本語 ―ポスト・モダン時代の日本文学 富岡幸一郎
第一回 文学は時代を映す鏡である
村上春樹の小説言語
村上春樹の『1Q84』は昨年から今年にかけて、出版界とくに小説の世界で大きな話題となった。3冊の累計部数が370万部をこえたともいわれる。本が売れなくなったという時代、これは異例のことだろう。映画化されてその原作としての本が注目されるというパターンとも違う。
やはり村上春樹の小説の文章が、この時代の読者を魅きつけているのは間違いない。村上人気は1980年代から続いている。『ノルウェイの森』(1987年)がミリオンセラーになったのは記憶に新しい。
村上のデビュー作は、1979年の雑誌『群像』の新人文学賞を受賞した『風の歌を聴け』である。その一節を少しだけ引用してみよう。
《僕は薄いビール・グラスの縁に唇をつけたまま黙って肯いた。鼠はそれっきり口をつむぐと、カウンターに載せた手の細い指をたき火にでもあたるような具合にひっくり返しながら何度も丹念に眺めた。僕はあきらめて天井を見上げた。10本の指を順番どおりにきちんと点検してしまわないうちは次の話は始まらない。いつものことだ》
作中の時期は、1970年8月に設定されており、「鼠」とは主人公の「僕」の友人のことである。
当時の選考委員の一人であった丸谷才一は、「二十九歳の青年がこれだけのものを書くとすれば、今の日本の文学趣味は大きく変化しかけてゐると思はれます。この新人の登場は一つの事件ですが、しかしそれが強い印象を与えるのは、彼の背後にある(と推定される)文学趣味の変革のせいでせう」と選評で述べている。
ポップな感覚と乾いた抒情。現代アメリカ小説やジャズ音楽などのアメリカ文化の影響も指摘されたが、この「文学趣味」の「変化」は、ただ新しい外国文学の影響というものだけではなかった。
そもそも外国文学の影響ということをいえば、明治期の文学以来、近代日本小説はさまざまな変容を重ねてきた。明治20年に『浮雲』を著わし、日本の近代小説の出発点をつくった二葉亭四迷も、東京外国語学校でロシア語を学び、ツルゲーネフの『あひゞき』を日本語に翻訳し、その訳文は、島崎藤村、国木田独歩、田山花袋などの作家たちがこれを愛誦(あいしょう)したという。言文一致体といわれる近代の口語散文は、まさに西洋文学の翻訳からはじまったのだ。
村上春樹もこの点では同じである。村上氏が若い頃から現代アメリカ文学を好んで読み、のちにサリンジャーの新訳を出版し話題にもなったが、1979年のデビュー当時、私はたまたま作家と直接に会う機会があり、そこで面白い話を聞いた。
それは『風の歌を聴け』の草稿を書いたとき、ふつうに日本語で書き出したが、自分が表現したいものがうまく文章に乗ってこない。そこで一度英文で書き、それを日本語に訳してみたという。もちろんこれも決して特別なことではなく、それこそ二葉亭らの近代日本語は外国語や漢語や和文との葛藤からつくり出されたのであり、古くは外国語(漢字)を借りて日本語の音を文字化した万葉仮名の歴史まで遡行できようが、ここでいいたいのはそのことではない。
村上氏が翻訳作業のようにして自らの小説の文章(日本語)を手に入れたのは、たんに個人的な言葉の営みではなく、文学の言葉をめぐる時代の大きな変化が、そこに深く関わったのではないかということである。 ここで日本の近代文学史をざっと辿ってみよう。
明治近代化からおよそ70年を経て、昭和10年前後の時期に、日本文学はひとつのピークをむかえる。プロレタリア文学からの転向文学としての中野重治の『村の家』、近代日本文学の最高傑作といってもよい島崎藤村の『夜明け前』、西洋のモダニズムを通過して日本人の美意識をとらえた川端康成の『雪国』などをあげることができよう。
そして、この昭和の十年代に青春期をむかえ、マルクス主義をはじめとした西洋の近代思想の洗礼を受け、戦争体験を経て書き出した作家たち──戦後文学と呼ばれる作家たちは、昭和20年からおよそ25年間、四半世紀にわたって多様かつ多彩な文学世界を創造した。
戦後派とも呼ばれる彼らは、1970年代半ばぐらいに、その代表作、ライフワークを発表し終える。野間宏、武田泰淳、埴谷雄高、椎名麟三、福永武彦、堀田善衞、中村真一郎、また三島由紀夫、島尾敏雄、安部公房等々、その文学の内実をひとまとめにすることはできないが、彼らの時代の文学は、おおきくいって明治以来の近代小説の流れの継承と展開のなかにあった。たしかに戦前の私小説などの伝統的な作風とは異なる、世界文学の水準に迫る思想的内容と新しい文体をつくり出したのであるが、広い視点で見れば、1970年代半ばまでの戦後文学も、「近代(モダン)」という価値を土台にしていたといってよい。
「近代(モダン)」とは、では何か。
近代とは何か
ひとつは、それは社会なりこの世界が〈進化〉するという考え方である。明治国家の日本の最大のイデオロギー、それはハーバート・スペンサーの社会進化論である。福沢諭吉が『文明論之概略』で表わした近代=文明という思想、すなわち「野蛮は半開に進み、半開は文明に進み、その文明も今まさに進歩の時なり」という進歩史観である。この意味では資本主義の矛盾(貧富の格差など)が、階級闘争を生み、社会主義国家となり、やがてユートピアとしての共産主義社会に至るという思想も、まさに「近代」主義的な発想のなかにある。西欧近代はこうした「近代(モダン)」の価値観によって支えられてきた。そして文明開化の日本も、この「近代化」を大目標として、戦前は「富国強兵」を、戦後は「経済大国」を目ざしてひた走って来たわけである。
日本の近代文学もまた、この「近代(モダン)」との同化と反発と葛藤を、文学の言葉のなかで表現してきた。
しかし、1970年代後半以降、このモダンの価値、普遍的な真理や理想社会を目ざす理念や物語が疑われ出した。ポスト・モダンという思想の標語が流行するのは、まさに1980年代からである。
ジャン=フランソワ・リオタールというフランスの哲学者は、『ポスト・モダンの条件』(1979年)という本のなかで、それを「大きな物語の失墜」と呼んだ。真理を求めてやまない哲学や科学的な知にたいする正当化の言説が失墜する、というのである。
日本でもこの時期に、現代思想といわれる領域で、しきりにポスト・モダン論が語られた。しかし、それはフランスの現代哲学の難解な翻訳言語の専門的なジャーゴン(仲間内の言葉)にとどまっていたように思う。
むしろ、村上春樹の登場に代表されるように、文学、小説の言葉の地平において、それまでの近代文学とはあきらかに異なった文体(スタイル)が出現してきたのである。
そして、その文体(スタイル)は、ポスト・モダンという思想ではなく、ポスト・モダンという状況、まさにその「時代の空気」を先取りしたかたちで映し出していた。
《僕がジェイズ・バーに入った時、鼠はカウンターに肘をついて顔をしかめながら、電話帳ほどもあるヘンリー・ジェームスのおそろしく長い小説を読んでいた。
「面白いかい?」
鼠は本から顔を上げて首を横に振った。「でもね、ずいぶん本を読んだよ。この間あんたと話してからさ。『私は貧弱な真実よりも華麗な虚偽を愛する。』知っているかい?」
「いや。」
「ロジェ・ヴァディム。フランスの映画監督さ。こんなのもあった。『優れた知性とは二つの対立する概念を同時に抱きながら、その機能を充分に発揮していくことができる、そういったものである。』」
「誰だい、それは?」
「忘れたね。本当だと思う?」
「嘘だ。」
「何故?」
「夜中の3時に目が覚めて、腹ペコだとする。冷蔵庫を開けても何も無い。どうすればいい?」
鼠はしばらく考えてから大声で笑った。僕はジェイを呼んでビールとフライド・ポテトを頼み、レコードの包みを取りだして鼠に渡した。
「なんだい、これは?」
「誕生日のプレゼントさ。」
「でも来月だぜ。」
「来月にはもう居ないからね。」
鼠は包みを手にしたまま考えこんだ。
「そうか、寂しいね、あんたが居なくなると。」鼠はそう言って包みを開け、レコードを取り出してしばらくそれを眺めた。
「ベートーベン、ピアノ協奏曲第3番、グレン・グールド、レナード・バーンステイン。ム……聴いたことないね。あんたは?」
「ないよ。」
「とにかくありがとう。はっきり言って、とても嬉しいよ。」》
ヘンリー・ジェームスの「長い小説」やベートーベンの「ピアノ協奏曲」の話などが会話に挿入されているが、ここでは教養主義的な価値は何も語られてはいない。それらは「ビールとフライド・ポテト」との相対性のなかに置かれている。ポスト・モダン状況においては、絶対的なもの・普遍的なものが物語として語られることはないのだ。
戦後文学の代表的作家の野間宏は、文学(小説)とは人間の「全体」をとらえることができるといった。「生理、心理、社会の三つの要素を明らかにし、それを総合する」(「私の小説作法」)として「全体小説」の概念をかかげた。これはフランスの実存主義の哲学者であり、また小説家としても活躍したサルトルなどが主張してきたことでもあるが、近代・戦後文学がそのようにこの世界と個人をめぐる「全体」に関わり、「総合」しようとする志向を持っていたのにたいし、ポスト・モダン状況はそうした世界像の解体から出発しているのである。中心的な軸はない。中枢が全体を司るのではなく、端末的なバラバラになった世界のカケラがそこかしこに広がっている。
ポスト・モダン状況の文学の言葉は、その散乱した世界のカケラを拾いあげ、新たなモザイクとして呈示してみせる。普遍・理想・典型の物語はもはや成り立たなくなっている。
しかし、これは決して悲観的なことでも、まして文学そのものの衰弱や死でもない。
それはこれから具体的に取りあげていきたい現代文学の言葉の世界をぜひ見ていただきたい。
三島由紀夫の認識
三島由紀夫は、村上春樹が『風の歌を聴け』で作中の時間として設定した1970年に自決したが、その直前、『日本文学小史』という日本の古典文学を論じたエッセイを遺している。古事記、万葉集からはじまり江戸期の近世文学(近松・西鶴・芭蕉・馬琴)といった、この国の千年を貫く日本語の世界を、ブリリアントな独自の視点から論じようと試みた文学史であった。残念ながらその死によって源氏物語を少しばかり論じたところで未完に終った。しかし、古今和歌集にふれた個所で、作家は、ここで「日本語というものの完熟」を成就したという。古今和歌集の日本語こそは「本当の意味の古典美」を示しているという。そして、それは日本人の「文化」の「亭午」すなわち「白昼(まひる)」である、と。
さらにこう記している。
《文化の白昼(まひる)を一度経験した民族は、その後何百年、いや千年にもわたって、自分の創(つく)りつつある文化は夕焼けにすぎないのではないかという疑念に悩まされる。明治維新ののち、日本文学史はこの永い疑念から自らを解放するために、朝も真昼も夕方もない、或る無時間の世界へ漂い出た。この無時間の抽象世界こそ、ヨーロッパ文学の誤解に充ちた移入によって作り出されたものである。かくて明治以降の近代文学史は、一度としてその「総体としての爛熟」に達しないまま、一つとして様式らしい様式を生まぬまま、貧寒な書生流儀の卵の殻を引きずって歩く羽目になった》(『日本文学小史』昭和47年11月刊)
この三島由紀夫による、日本近代文学への挑戦の言葉を、今日どう受けとめることができるのか。三島自身もまたこの明治以降の「無時間の抽象世界」のなかで、自らの文学を創造してきたのはいうまでもない。
この鋭利でチャレンジングな三島の未完の文学史が書かれてから、40年の歳月を経て、今われわれが目にしているのは、近代日本文学百数十年の終焉の風景なのである。
それは同時に、モダンという長いトンネルを抜け出たところで、新たに模索されつつある、ポスト・モダン状況における日本語の世界に他ならない。
近代日本文学が、三島のいうように「一つとして様式」を生まなかったと断じきることはできないように思うが、「近代(モダン)」という西洋近代をそもそものモデル(模型)とすることから出発した、この国の近代文学は、その限界をおのずから形成し、つねに西洋近代文学との比較意識、そのコンプレックスのなかに置かれてきたのはたしかであろう。
しかし、そのモダンの絶対的であり普遍的であると信じられてきた価値は、すでに大きく揺らぎ、崩落しているのだ。
「近代(モダン)」とは、中世社会に続く新しい社会を実現したのではなく、むしろ新しい安定した秩序と社会をつくれないでいる、人類史における大きな逸脱の過渡期の時代である。―第一次大戦後に非暴力による社会革命を目ざしたドイツの社会哲学者グスタフ・ランダウアーはこういう。(『レボルツィオーン』大窪一志訳 同時代社 2004年刊)
ポスト・モダンの今日的状況を、近代という「大きな逸脱の過渡期の時代」から脱却しつつあるととらえることはできないだろうか。その来るべき「時代の姿」は未だ霧に包まれたように定かではないが、「文学は時代を映す鏡である」ということはいえるのではないか。
1979年の村上春樹の登場は、日本の文壇の小さな事件であった。しかし、その後30年を経てあきらかになっているのは、21世紀の現代の日本語の文学は、ポスト・モダニズムの世界で、むしろこの国の千年を越える日本語の豊饒な世界に、自在に自由にその書き手の文体(スタイル)からアクセスしうるようになっている、いや現にそうした小説世界が世代を貫いて展開されているということである。
したがって、ここで試みたいのは文芸時評のスタイルを採って、このポスト・モダン時代の日本語文学の面白さと可能性をさぐることなのである。
(参照文献)
村上春樹『風の歌を聴け』(講談社文庫)
三島由紀夫『日本文学小史』(『小説家の休暇』新潮文庫所収)
※本連載では多くの文学作品を取り扱う予定だが、読者の便宜を考え、手に入りやすい版の書誌情報を末尾に挙げる。