おすすめマンガ時評『此れ読まずにナニを読む?』
第97回『ぼくらのよあけ』今井哲也(講談社)
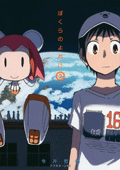
(c)今井哲也/講談社
年末恒例のマンガベスト企画では、昨年2011年のベストに何人かの「マンガ読み」のひとがこの作品をあげていた。単行本一巻刊行時である。多くのマンガベスト企画は、年の区切りが10〜11月なので、どうにか二巻(完結)を、2012年の雑誌のベスト企画で答えることができた。かろうじて「間に合った」のだ。ある意味「周回遅れ」である。年間のマンガ刊行点数が多く、「マンガ読み」たちがいつも先端を見がちになる状況下、わずか一年前の作品でも顧みられなくなりがちな昨今、こうした「周回遅れ」にも多少の意味はあるだろうと自己弁護をしておく。
SFマンガである。舞台は近未来、2038年の杉並区内の団地である。主人公は宇宙にあこがれる小学四年生男子。人工知能を実装した家庭用ロボットが普及した社会だ。「オートボット」と呼ばれるそれは、もちろん主人公の家庭にもいて、なにかと彼の世話を焼いている。物語は、このオートボット・ナナコと主人公・ゆうまの交流と別れを縦軸に、宇宙から地球に落下した知性体「二月の黎明」とコンタクトした主人公ら子供たちが「二月の黎明」を母星に返すべく射出するまでを横軸に、少年の夏の日を描くジュブナイルでもある。その筆致は繊細で、団地に暮らす子供たちの小さな社会もきちんと描かれる。言葉の最良の意味で「児童文学的」と言っていいだろう。
初見時といまとで評価が180度変わったのはなぜかについて、しっかり説明をしないといけないだろう。弁明といえば弁明だが、私と同じように、この作品をはじいている読者がいないとも限らない。それに、私の初期の「拒絶」は、個人的な好悪の感情というよりも、どうやら時代的なものでもあるように思えるのだ。
それは、「未来」を語ることがすでにノスタルジックな感情の引力とともにあるという逆説である。そもそも未来社会の物語なのに、すでに高齢化・老朽化が問題視されている「団地」を舞台に持ってくるセンスを疑ったのだ。「こうあったかもしれない」過去を、想像上の未来に投影する物語だと即断してしまったのだ。
この予測は、いい方向に裏切られた(そのため、評価は180度変わった)。『ぼくらのよあけ』の舞台である2038年の団地は、現在と同じくらいか、それ以上に高齢化・過疎化が進んだ場所だ。周囲の住宅街の様子は現在とさほど変わっていないようだが、そのことは、作中でも「ここは外見ほど 住人が多くない のだな」「うん」「もうほとんど じーちゃん ばーちゃん ばっかりだよ」という会話で説明される。このやりとりが、外宇宙という、まさに「外部」から来た「二月の黎明」と、団地で生まれ育った子供である主人公・ゆうまの会話であることは、少し気に留めておいていいかもしれない。この物語の、この時代の子供たちは、生まれたときから老朽化した団地で育っているのだ。ここには、かつて団地が次々と建てられたころのような、明るく快適な生活を約束する輝かしい「未来」の象徴もなければ、私たちの世代が持ってしまうような、それこそ「原風景」的なノスタルジーもない。本作は「団地」という意匠の意味を積極的に読み替えようとしているようにも思える。
いま私は「団地」を、かつて輝かしい「未来」の象徴だったと言った。ここに逆説がある。話は団地に限らない。「未来」が輝かしいものとして物語化されること自体が、すでに「懐かしい」ものであるという逆説がある。
「未来」を輝かしいものとして語る感覚は、素朴な進歩史観と言ってもいいのだが、むしろもっと日常の暮らしに密着した感覚に支えられていたと思う。それは日々の暮らしが社会の進歩によって、より快適に、清潔になっていったことに担保されていたのではないかと考えるのである。科学技術への素朴な憧れも、その「より快適に、清潔に」というセンスに支えられてきたのではないか。その意味で「団地」は「未来」の象徴である。
だが、そうした生活のインフラ整備は、日本においては1980年代には完了した。人々の「より快適に、清潔に」という欲望は飽和したと言ってもいい(家電メーカーの迷走ぶりは、まさにこの飽和に適応できていないことによるだろう)。
しかし、未来はいやがおうにもやってくる。少子化が進行しているとはいえ、日本の人口がこのまま減少を続けるだろうとはいえ、子供が生まれないわけではない。そして新しくこの世界にやってきた子供たちには、私たちが勝手に持ってしまっている「過去へのノスタルジー」などとは関係なく、「未来」がある。本作が素晴らしいのは、「宇宙」への憧憬や、「進歩」への希求といった、ともすれば私たちがノスタルジックな視線で見てしまうもの――あるいは、若い世代ですら、過去の物語的な枠組みでとらえてしまうもの――を、「これから」の子供たちの視線でとらえなおそうとしているかに読めるからだと思う。「懐かしい未来」という物語的逆説の力を用いながら、その逆説の打破を志向しているように見えるのだ。
じつのところ、このレビューは、あえて物語の具体的な展開に触れずに書いている。それはいわゆる「ネタバレ」を避けるためだ。ひとつだけ、若干「ネタバレ」になるかもしれない記述を許してほしいのだが、この物語の特筆すべき点は、宇宙からの知性体と関わった「子供たち」が親子二代に渡っていることだ。主人公・ゆうまの両親もまた、「二月の黎明」と関わり、彼を団地の屋上で眠らせていたのだ。地球人が彼を宇宙に戻しうるような技術的なブレイクスルーを期待してのことだ。そして、そのブレイクスルーが意外な形で行われていたことが、作中で明確に語られる。
もうひとつ、親子二代に渡って同じ場所に生きる人々の「物語」は、昨今の地方を舞台にしたマンガとも通じるものがあるように思う。それは旧来的な閉鎖的で旧弊な「田舎」という村落共同体の秩序の抑圧が壊れた後の「地方」を「地縁・血縁とゆるやかに接続されるコミュニティ」として描く物語群だ。その意味では、本作の団地は、すでに「村」である。この物語が2038年という年号とともに2010年代初頭に描かれたことは、あるいは今後作られるであろう「物語」の方向を示唆するものかもしれない。
(伊藤剛)
