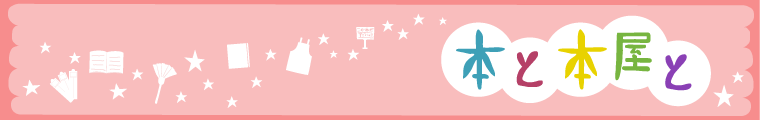本と本屋と
第16回 本屋は灯る
早番で帰るときは、振り向かずにそそくさと去る。店を出て、たまに気まぐれに後ろを仰ぐと、ガラス張りの高いビルが煌々と光っている。エスカレーターで人が上り下りしているのが見える。たくさんの知らないお客さんたち、たくさんの知っている店員たち。あのなかに150万冊の本があり何百人かの人がいて、みんな本のために動きまわっている。電車のなかから人の家の窓を眺めたときのような、しんとした気持ちになる。
そんな感傷には関係なく、本屋はいつも明るい。小さな活字を追わなければいけないのだから当然なのだろう。棚のほこりも私の毛穴も人目にさらされる。音は筒抜け、物は丸見えなのが本屋なのだ。
あまりに明るすぎるのでは、と近ごろ思う。間接照明ばやりのご時世に、色気がない。ブックフェアを外部の人にプロデュースしてもらったときも、
「真ん中の棚にスポットライトを当てましょう」
と提案されたのに、コンセントの位置や、そもそも周りが明るすぎてスポットライトが目立たない、といった理由で断念した。
陰が欲しい。白い光の下では、なかなかぼんやりできない(してはいけないと知りつつ)。暗い書斎に入りこんでこっそり人の本に読みふけるような背徳感が欲しい。
コンビニの24時間営業が取りざたされているのも気になる。温暖化がどうとかいう前に、電気を消したい。少し休みたい。それだけだ。
朝、開店前には電気をつけずに過ごす。窓の近くの本ならじゅうぶん背表紙が読める。雨の日は真っ暗になる。喫茶室は一面がガラス張りで、朝の光が差してくる。用がなくても、そちらに向かって歩いていきたくなる。
夕方は西日がすごくて、夏はパソコンの画面が真っ黒になって読めない。本も静かに日焼けしていく。
閉店まで残るときは、自分で電気を消して帰る。消したあとで、
「あ、この本戻さなきゃ」
と棚に行ってみると、全くもって何も見えない。もう何年も毎日向きあっている棚なのに、闇のなかでは他人だ。目隠しをしたまま本の場所を当てる、というカリスマ書店員がテレビに出ていたけれど、私には無理だ。暗い本屋も、無理なのかな。いや、闇でなくても明るすぎなければいい。
私が夜までさんさんと照らされているとき、外から店の灯りを見て、
「これから本屋に行くぞ」
とわくわくしてくれる人がいることを、せめて願う。
入ったら真っ暗で、
「ようこそ、匂いと手触りでお選びください」
とどこからか呼びかけられ、エレベーターで適当な階まで上って、棚づたいに歩いて、なんとなく手に触れた本を買って出て、思いがけない本を手にしている。いつか「闇鍋」ならぬ「闇棚」でもして遊べたら、なんてことも、ついでに願う。
そんな感傷には関係なく、本屋はいつも明るい。小さな活字を追わなければいけないのだから当然なのだろう。棚のほこりも私の毛穴も人目にさらされる。音は筒抜け、物は丸見えなのが本屋なのだ。
あまりに明るすぎるのでは、と近ごろ思う。間接照明ばやりのご時世に、色気がない。ブックフェアを外部の人にプロデュースしてもらったときも、
「真ん中の棚にスポットライトを当てましょう」
と提案されたのに、コンセントの位置や、そもそも周りが明るすぎてスポットライトが目立たない、といった理由で断念した。
陰が欲しい。白い光の下では、なかなかぼんやりできない(してはいけないと知りつつ)。暗い書斎に入りこんでこっそり人の本に読みふけるような背徳感が欲しい。
コンビニの24時間営業が取りざたされているのも気になる。温暖化がどうとかいう前に、電気を消したい。少し休みたい。それだけだ。
朝、開店前には電気をつけずに過ごす。窓の近くの本ならじゅうぶん背表紙が読める。雨の日は真っ暗になる。喫茶室は一面がガラス張りで、朝の光が差してくる。用がなくても、そちらに向かって歩いていきたくなる。
夕方は西日がすごくて、夏はパソコンの画面が真っ黒になって読めない。本も静かに日焼けしていく。
閉店まで残るときは、自分で電気を消して帰る。消したあとで、
「あ、この本戻さなきゃ」
と棚に行ってみると、全くもって何も見えない。もう何年も毎日向きあっている棚なのに、闇のなかでは他人だ。目隠しをしたまま本の場所を当てる、というカリスマ書店員がテレビに出ていたけれど、私には無理だ。暗い本屋も、無理なのかな。いや、闇でなくても明るすぎなければいい。
私が夜までさんさんと照らされているとき、外から店の灯りを見て、
「これから本屋に行くぞ」
とわくわくしてくれる人がいることを、せめて願う。
入ったら真っ暗で、
「ようこそ、匂いと手触りでお選びください」
とどこからか呼びかけられ、エレベーターで適当な階まで上って、棚づたいに歩いて、なんとなく手に触れた本を買って出て、思いがけない本を手にしている。いつか「闇鍋」ならぬ「闇棚」でもして遊べたら、なんてことも、ついでに願う。