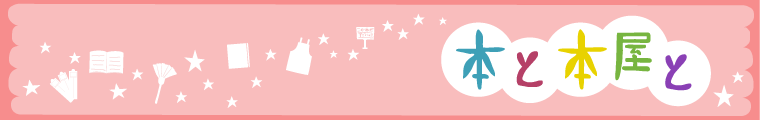本と本屋と
第7回 閉じた本
「まだ誰も開けていない聖書が店頭にないでしょうか」
と電話で聞かれた。難しい。しかし気持ちはよくわかる。一度開かれた本、読まれた本にはしるしが残る。表紙に折り目がついたり、ページが軽く開いたり。本を配送するときには傷みや乱丁がないか中を確かめる必要があるけれど、どうも気が引けて、おそるおそるめくる。本の表紙を開くことが物語の扉を開くことにたとえられるように、買った本をはじめて開く瞬間はいつだって楽しみだ。
ふだん閉じているからこそ、開かれた本は威力をもつ。『花押のせかい』(望月鶴川、朝陽会、税込1,260円)が発売されたとき、サイン会のお話を頂いた。店の都合でできなかったのだが、思いついて「パネル展にしませんか」と言ってみた。本の図版を抜きだして説明をつけた、大きなパネルを作ってもらった。それを壁にかけて前に本を積んだら、1日に2、3冊のペースで売れだした。1ヶ月続けたら、サイン会をした別の書店とほぼ同じ数が売れた。パネルを飾るだけで売れ行きがぐんと上がる、なんて楽なんだろうと思った。(パネルは出版社の方につくって頂き、設営も手伝ってもらった。楽なのは私だけなのだが)
以来、「これは」と思うビジュアル本が出るとパネル展を提案して、やらせてもらっている。図や写真の吸引力はすごい。『GHQカメラマンが撮った戦後ニッポン』(ディミトリー・ボリア、アーカイブス出版、税込4,935円)や『カンボジアの子どもたち』(遠藤俊介、連合出版、税込2,625円)といったそこそこ値がはるものも、勢いよく売れていく。ひょっとすると、ビジュアル本に限らず、文字だけの任意の1ページをパネルにしても売れる本はあるのでは?という気がしている。目立つ、という理由だけではなく。
広告や書評を見ていいなと思っても、実際に本を見たら想像と違ったということがよくある。そういうとき、「違った」ことは中の文章をきちんと読まなくても、ぱらぱらとめくるだけでだいたいわかる。逆に、開かれた1ページに惹かれることも、きっとある。
11月から刊行される小学館の『全集日本の歴史』の販促物は、最初の数十ページだけ印刷された束見本と、本を開いて立てておけるスタンドだった。さすがお金あるんだねといいつつ、これはどんなPOPやあおり文句にも優るだろうなと思った。本の中身が一番強い。それがふだん秘められているのはもったいない。
一度買われると、本は開かれる。隠しようがないくらいに。いくらカバーをかけても、うしろから覗かれれば丸見えである。電車で前に立っている人が読んでいる本はつい見てしまう。マンガに週刊誌、資格の参考書が多い。小説はなぜかみんな推理小説に見える。タイトルも著者もわからないまま、字面だけで勝手に「好みだ」「好みでない」とか思いながら、乗っている。携帯電話のように覗き見防止シートがあったら欲しい人もいるだろうか。
棚から函入りの本を出すと、本にかかっているパラフィン紙がよれて破れていた。誰かが手にとり、このきつい函から本を出して開いたのだ。ずっと売れていないけれど、誰からも顧みられなかったわけではなかった。それがわかって、返品するのをやめてまた棚に戻した。
函や値段に気圧されて「買えないな」と思ったとしても、せっかく本屋に来たのなら、中を開けてみて欲しい。コピーも値引きもできない本屋にできることは、そこにある本を手にとっていただくこと、それだけだから。
と電話で聞かれた。難しい。しかし気持ちはよくわかる。一度開かれた本、読まれた本にはしるしが残る。表紙に折り目がついたり、ページが軽く開いたり。本を配送するときには傷みや乱丁がないか中を確かめる必要があるけれど、どうも気が引けて、おそるおそるめくる。本の表紙を開くことが物語の扉を開くことにたとえられるように、買った本をはじめて開く瞬間はいつだって楽しみだ。
ふだん閉じているからこそ、開かれた本は威力をもつ。『花押のせかい』(望月鶴川、朝陽会、税込1,260円)が発売されたとき、サイン会のお話を頂いた。店の都合でできなかったのだが、思いついて「パネル展にしませんか」と言ってみた。本の図版を抜きだして説明をつけた、大きなパネルを作ってもらった。それを壁にかけて前に本を積んだら、1日に2、3冊のペースで売れだした。1ヶ月続けたら、サイン会をした別の書店とほぼ同じ数が売れた。パネルを飾るだけで売れ行きがぐんと上がる、なんて楽なんだろうと思った。(パネルは出版社の方につくって頂き、設営も手伝ってもらった。楽なのは私だけなのだが)
以来、「これは」と思うビジュアル本が出るとパネル展を提案して、やらせてもらっている。図や写真の吸引力はすごい。『GHQカメラマンが撮った戦後ニッポン』(ディミトリー・ボリア、アーカイブス出版、税込4,935円)や『カンボジアの子どもたち』(遠藤俊介、連合出版、税込2,625円)といったそこそこ値がはるものも、勢いよく売れていく。ひょっとすると、ビジュアル本に限らず、文字だけの任意の1ページをパネルにしても売れる本はあるのでは?という気がしている。目立つ、という理由だけではなく。
広告や書評を見ていいなと思っても、実際に本を見たら想像と違ったということがよくある。そういうとき、「違った」ことは中の文章をきちんと読まなくても、ぱらぱらとめくるだけでだいたいわかる。逆に、開かれた1ページに惹かれることも、きっとある。
11月から刊行される小学館の『全集日本の歴史』の販促物は、最初の数十ページだけ印刷された束見本と、本を開いて立てておけるスタンドだった。さすがお金あるんだねといいつつ、これはどんなPOPやあおり文句にも優るだろうなと思った。本の中身が一番強い。それがふだん秘められているのはもったいない。
一度買われると、本は開かれる。隠しようがないくらいに。いくらカバーをかけても、うしろから覗かれれば丸見えである。電車で前に立っている人が読んでいる本はつい見てしまう。マンガに週刊誌、資格の参考書が多い。小説はなぜかみんな推理小説に見える。タイトルも著者もわからないまま、字面だけで勝手に「好みだ」「好みでない」とか思いながら、乗っている。携帯電話のように覗き見防止シートがあったら欲しい人もいるだろうか。
棚から函入りの本を出すと、本にかかっているパラフィン紙がよれて破れていた。誰かが手にとり、このきつい函から本を出して開いたのだ。ずっと売れていないけれど、誰からも顧みられなかったわけではなかった。それがわかって、返品するのをやめてまた棚に戻した。
函や値段に気圧されて「買えないな」と思ったとしても、せっかく本屋に来たのなら、中を開けてみて欲しい。コピーも値引きもできない本屋にできることは、そこにある本を手にとっていただくこと、それだけだから。