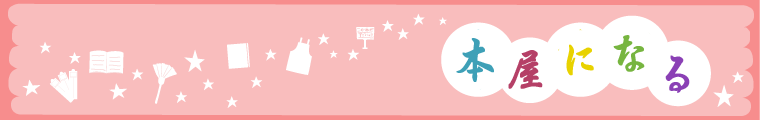本屋になる
第13回 本を食べる
大学生のとき、「これだけは読んでおくべき日本文学」というリストが配られて、図書館や古本屋で探しては読んでいった。勉強のためにというよりはひまつぶしだった。文庫4巻分の長篇も、全集にしか入っていない短篇もあった。
とにかくリストを消化したかったので、ただ字を追うだけ、ページをめくるだけになる本が大半だった。表面だけなめた本は味もろくに感じられず、何が書かれていたかも覚えていないし、栄養にもなっていない。
ごくまれに、何度も読み返したくなる一節に出くわすことがあった。なぜだか揺さぶられる。どこからこんな言葉が出てきたのかと思い、自分から出てこなかったことがくやしくなる。声に出したり書きうつしたりしてみても自分のものにはならない。もどかしい。パクリとまるごと食べられたら満足できるのに。
『文字の食卓』(正木香子、本の雑誌社)を読みながらそんな学生のころを思いだし、そうか書体ごと写さなければいけなかったんだ、と気がついた。
「たっぷりの うるおいがしみこんで、満たします。」
明朝体のひとつである〈A1明朝〉の使用例として、資生堂の商品パンフレットの一文が挙げられている。著者いわく、A1明朝は「滴る文字」。しずくを含んでふくらんだような文字だ。この書体だからこそ、化粧水が肌にぐんぐん入ってくる感触が想像できる。これをボールペンで書いたら、この書体が演出する〈「朝摘み感」ともいうべきみずみずしさ〉は完全に失われる。
約40の書体について、その書体が使われた本や雑誌や歌詞カードの引用とともに、著者の印象や記憶が語られていく。どういう本か想像もつかないのに、発売前から楽しみにしていた。
11月初めに福岡に行ってリブロ福岡天神店で買った。プロフィールを見て、著者が福岡出身で私と一歳しか違わないのを知った。
年が近いからか、「見本」のほとんどに見覚えがある。図書館で借りた絵本、妹と夢中になって読んだマンガ、面白そうな号だけ買っていた雑誌、私は読んだことがなくてもクラスの誰かが持っていた本。
ごく個人的な感覚や体験にもとづいたエッセイなのに、共感できる。自分も体験していながら言葉にできなかった記憶を言い当てられているような。「キャラメルの文字」ってどんな文字? と首をかしげ、ページをめくって現れた『月夜のみみずく』の引用に納得する。「石井細明朝体横組み用かな」。キャラメルを噛みしめたときの引っかかる歯ごたえと香ばしさを、確かにこれまでも感じてきた。
書体という概念も知らないうちから違いを見分けていたという正木さんには、「絶対音感」ならぬ「絶対字感」とでもいうものがあるのだろう。私も音痴なりに聞き覚えてきたものがあるのだと、初めてわかった。マンガのふきだしの文字を見るだけで絵まで浮かんできたり、絵本の文字から表紙を思い出したり。ストーリーはすっかり忘れているのに。
自分の知らないところで、読んできた本たちは体に残っているのかもしれない。ざっととばし読みしただけでも、最後まで読みきれなくても、目は何百、何千という文字をうつしだしている。本を食べたい、自分のものにしたいという夢は最初から叶っていたのかも。
そうだとしたら、ただ本を眺めていただけの時間も無駄ではなかった気がしてくる。この文字たちとすごした時間は、私のものだ。
給食に出てきたなつかしいパンや牛乳を食べながら、
「25年前、あなたはこんな味を、こんな匂いを感じていたんだよ」
と、隣の席の子に教えてもらっているような読書だった。
11月下旬に同じ本の雑誌社から出た『捨てる女』(内澤旬子)は、著者の内澤さんが身のまわりの一切合財をひたすら捨てる話で、たまった本の始末にはとりわけ苦労されたようだ。
内容がつまらなくても文字すら読めなくても、印刷と製本が面白い本なら買ったという。本を選ぶ基準が人と違うために、手放そうとしても売値がつかない。買い集めるのに大金を要し、長年にわたって住居を圧迫したうえ、処分するにも手間のかかることを嘆きつつ、それでも買ったことを悔やまない。
こういう本の食べかたもあるんだ。
あなたの好きなように召し上がれと言ってもらえたような、うれしい二冊だった。
とにかくリストを消化したかったので、ただ字を追うだけ、ページをめくるだけになる本が大半だった。表面だけなめた本は味もろくに感じられず、何が書かれていたかも覚えていないし、栄養にもなっていない。
ごくまれに、何度も読み返したくなる一節に出くわすことがあった。なぜだか揺さぶられる。どこからこんな言葉が出てきたのかと思い、自分から出てこなかったことがくやしくなる。声に出したり書きうつしたりしてみても自分のものにはならない。もどかしい。パクリとまるごと食べられたら満足できるのに。
『文字の食卓』(正木香子、本の雑誌社)を読みながらそんな学生のころを思いだし、そうか書体ごと写さなければいけなかったんだ、と気がついた。
「たっぷりの うるおいがしみこんで、満たします。」
明朝体のひとつである〈A1明朝〉の使用例として、資生堂の商品パンフレットの一文が挙げられている。著者いわく、A1明朝は「滴る文字」。しずくを含んでふくらんだような文字だ。この書体だからこそ、化粧水が肌にぐんぐん入ってくる感触が想像できる。これをボールペンで書いたら、この書体が演出する〈「朝摘み感」ともいうべきみずみずしさ〉は完全に失われる。
約40の書体について、その書体が使われた本や雑誌や歌詞カードの引用とともに、著者の印象や記憶が語られていく。どういう本か想像もつかないのに、発売前から楽しみにしていた。
11月初めに福岡に行ってリブロ福岡天神店で買った。プロフィールを見て、著者が福岡出身で私と一歳しか違わないのを知った。
年が近いからか、「見本」のほとんどに見覚えがある。図書館で借りた絵本、妹と夢中になって読んだマンガ、面白そうな号だけ買っていた雑誌、私は読んだことがなくてもクラスの誰かが持っていた本。
ごく個人的な感覚や体験にもとづいたエッセイなのに、共感できる。自分も体験していながら言葉にできなかった記憶を言い当てられているような。「キャラメルの文字」ってどんな文字? と首をかしげ、ページをめくって現れた『月夜のみみずく』の引用に納得する。「石井細明朝体横組み用かな」。キャラメルを噛みしめたときの引っかかる歯ごたえと香ばしさを、確かにこれまでも感じてきた。
書体という概念も知らないうちから違いを見分けていたという正木さんには、「絶対音感」ならぬ「絶対字感」とでもいうものがあるのだろう。私も音痴なりに聞き覚えてきたものがあるのだと、初めてわかった。マンガのふきだしの文字を見るだけで絵まで浮かんできたり、絵本の文字から表紙を思い出したり。ストーリーはすっかり忘れているのに。
自分の知らないところで、読んできた本たちは体に残っているのかもしれない。ざっととばし読みしただけでも、最後まで読みきれなくても、目は何百、何千という文字をうつしだしている。本を食べたい、自分のものにしたいという夢は最初から叶っていたのかも。
そうだとしたら、ただ本を眺めていただけの時間も無駄ではなかった気がしてくる。この文字たちとすごした時間は、私のものだ。
給食に出てきたなつかしいパンや牛乳を食べながら、
「25年前、あなたはこんな味を、こんな匂いを感じていたんだよ」
と、隣の席の子に教えてもらっているような読書だった。
11月下旬に同じ本の雑誌社から出た『捨てる女』(内澤旬子)は、著者の内澤さんが身のまわりの一切合財をひたすら捨てる話で、たまった本の始末にはとりわけ苦労されたようだ。
内容がつまらなくても文字すら読めなくても、印刷と製本が面白い本なら買ったという。本を選ぶ基準が人と違うために、手放そうとしても売値がつかない。買い集めるのに大金を要し、長年にわたって住居を圧迫したうえ、処分するにも手間のかかることを嘆きつつ、それでも買ったことを悔やまない。
こやつらを買うのに、その何倍もの古書と出会い触れ合い、本がオブジェとしてどうあるべきなのかを考えながら、世界各地の古書店や骨董屋でこまかく眺め倒し、買うかどうかを真剣に検討してきたのである。エッセンスは十分自分の中に沈殿している。自分なりの「眼」はできたと思っている。何にも役に立てずに、頭の中の奥底に眠っているだけでも、いい。無形財産みたいなもの。無駄とは思わない。
こういう本の食べかたもあるんだ。
あなたの好きなように召し上がれと言ってもらえたような、うれしい二冊だった。