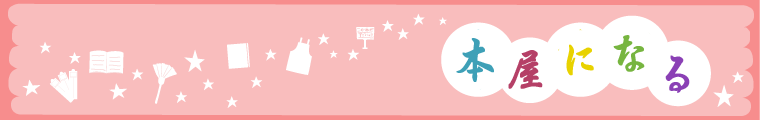本屋になる
第11回 本を出す
前回の「本を編む」というのは私にとって思いがけない動詞だった。今回の「本を出す」は「売る」よりも昔から、「読む」の次くらいにあったかもしれない。一生の夢として。小説を書いて文学賞に応募して本を出すのを想像していた。なにも書いていないのに。
7月末に沖縄の出版社のボーダーインクから本を出した。『那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた〈ウララ〉の日々』。小説ではなく本屋の本を、沖縄の出版社から出す。これもまた自分の妄想の及ばない、思いがけないできごとだった。
本のなかで一番古いのは、2009年に勤務先の書店のPR誌に書いた原稿である。その年の4月に開店した那覇店の話を書いた。こうやって沖縄の本屋の話を県外に伝えていけたらいいなと思い、そのあともどこかから原稿の依頼がもらえれば受けた。それが本にまとまるとは思わずに、ただ書いていた。
「本を出そう」
と言ってもらったとき、喜びつつも「まだ早すぎる」と躊躇した。その時点で沖縄に来て三年、古本屋を始めて半年しか経っていない。おまえに何がわかる、と自分でも思った。でもたとえ十年待ったところで、私は生粋のウチナーンチュにもまっとうな古本屋にも、一流の書き手にもなれない。それなら出そうと言ってくれる人がいるときに出してしまおう。
ばらばらな原稿を整理してくれたのは、もちろんボーダーインクの編集者である。内容が重なり、時系列が行きつ戻りつしている原稿を切貼し、一本の流れにして見せてくれたときはびっくりした。
「これ、あんがい早くできるかもね」
ためしに刷ってくれたゲラは思いのほか厚みがある。こんな本をどこから取り出してきたのだろうと、著者のはずなのに不思議になる。これが「本を編む」ということなんだ。
原稿をさらに書き足し、自分の文章にうんざりしながら校正した。一方では書名やカバーのデザイン、帯の色、本文用紙などについても話を進める。今までは本屋として意見を求められればなんとなく答えられたのに、自分の本となると判断が難しい。
ようやく校了しても、これでひと段落と涼しい顔はしていられない。今回は自分の本屋で仕入れるだけでなく、ほかの本屋にも働きかける必要があるわけで、これまた「本を営業する」という新しい動詞が出てくる。
沖縄県産本は全国の書店に自動的に配本されるというものではない。注文がなければ納品しないし、基本は買切である。県外は全体でたぶんこのくらい、県内は那覇を中心に配本してあとは何冊くらいで、と具体的な数字を重ねていく。古本屋に卸すなら掛率はいくら、何冊以上なら送料は版元負担と、ふだん本屋としてする話を逆の立場から考えると、また違って聞こえる。いつも「もう少しおまけしてくれてもいいのに」と思っていたのも、「ああ、これでギリギリなんだなあ」と納得する。
あの店が注文をくれたよ、と出版社の人がちらちら教えてくれる。ああ、この店がこんなに。おお、あの目利きの店が。たとえ一冊でも注文してくれたらうれしい。書店員は出版社の人をこんなに一喜一憂させられるんだ、といまさら知る。
一週間後の金曜日の午後に完成する、と言われた。印刷された紙も製本のようすも見ていないからどうも信じられない。ただそわそわと過ごす。
予定日の午前中に編集の人から、
「いま印刷所から納品されたよ。思ったより早かったね」
と電話があった。本当にできたんだ。でもやっぱり実感がない。出産の報告を受けた父親というのはこんな心境なのだろうか。
三時間後には自分の店に届けられた。この速さは県産本ならではだろう。梱包された束を目にすると、本の出来ばえを確かめるより先に、どんどん売らなければという気になる。
編集の人とねぎらい合いつつアイスコーヒーを飲んでいたら、いつも本を売ってくれるお客さまがいらした。
「本を出しました」
見せたら、買ってくれた。この本をこの世で初めて買ってくれた。私もまたこの本を初めて売った本屋になれた(ほかの書店にはこのあと納品に行くところだった)。
そのあとも入荷を知った人が来ては「おめでとう」と言いながらご祝儀がてら買ってくれる。さらにはお花までもらった。この感じ、なつかしい。そう、店を始めた日と同じだ。喜びよりも不安のほうが大きくてうつむいていても、まわりが盛り立ててくれて、なんとか元気を出せた。
開店した日はフワフワと落ち着かなかったのも、一週間もたてばなじんだ。この本が積み上がる風景にも、慣れるのだろうか。一日限りのイベントとも月刊誌に記事が載るのとも違う、これからしばらく続いていく日常が、また新しく始まった。
7月末に沖縄の出版社のボーダーインクから本を出した。『那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた〈ウララ〉の日々』。小説ではなく本屋の本を、沖縄の出版社から出す。これもまた自分の妄想の及ばない、思いがけないできごとだった。
本のなかで一番古いのは、2009年に勤務先の書店のPR誌に書いた原稿である。その年の4月に開店した那覇店の話を書いた。こうやって沖縄の本屋の話を県外に伝えていけたらいいなと思い、そのあともどこかから原稿の依頼がもらえれば受けた。それが本にまとまるとは思わずに、ただ書いていた。
「本を出そう」
と言ってもらったとき、喜びつつも「まだ早すぎる」と躊躇した。その時点で沖縄に来て三年、古本屋を始めて半年しか経っていない。おまえに何がわかる、と自分でも思った。でもたとえ十年待ったところで、私は生粋のウチナーンチュにもまっとうな古本屋にも、一流の書き手にもなれない。それなら出そうと言ってくれる人がいるときに出してしまおう。
ばらばらな原稿を整理してくれたのは、もちろんボーダーインクの編集者である。内容が重なり、時系列が行きつ戻りつしている原稿を切貼し、一本の流れにして見せてくれたときはびっくりした。
「これ、あんがい早くできるかもね」
ためしに刷ってくれたゲラは思いのほか厚みがある。こんな本をどこから取り出してきたのだろうと、著者のはずなのに不思議になる。これが「本を編む」ということなんだ。
原稿をさらに書き足し、自分の文章にうんざりしながら校正した。一方では書名やカバーのデザイン、帯の色、本文用紙などについても話を進める。今までは本屋として意見を求められればなんとなく答えられたのに、自分の本となると判断が難しい。
ようやく校了しても、これでひと段落と涼しい顔はしていられない。今回は自分の本屋で仕入れるだけでなく、ほかの本屋にも働きかける必要があるわけで、これまた「本を営業する」という新しい動詞が出てくる。
沖縄県産本は全国の書店に自動的に配本されるというものではない。注文がなければ納品しないし、基本は買切である。県外は全体でたぶんこのくらい、県内は那覇を中心に配本してあとは何冊くらいで、と具体的な数字を重ねていく。古本屋に卸すなら掛率はいくら、何冊以上なら送料は版元負担と、ふだん本屋としてする話を逆の立場から考えると、また違って聞こえる。いつも「もう少しおまけしてくれてもいいのに」と思っていたのも、「ああ、これでギリギリなんだなあ」と納得する。
あの店が注文をくれたよ、と出版社の人がちらちら教えてくれる。ああ、この店がこんなに。おお、あの目利きの店が。たとえ一冊でも注文してくれたらうれしい。書店員は出版社の人をこんなに一喜一憂させられるんだ、といまさら知る。
一週間後の金曜日の午後に完成する、と言われた。印刷された紙も製本のようすも見ていないからどうも信じられない。ただそわそわと過ごす。
予定日の午前中に編集の人から、
「いま印刷所から納品されたよ。思ったより早かったね」
と電話があった。本当にできたんだ。でもやっぱり実感がない。出産の報告を受けた父親というのはこんな心境なのだろうか。
三時間後には自分の店に届けられた。この速さは県産本ならではだろう。梱包された束を目にすると、本の出来ばえを確かめるより先に、どんどん売らなければという気になる。
編集の人とねぎらい合いつつアイスコーヒーを飲んでいたら、いつも本を売ってくれるお客さまがいらした。
「本を出しました」
見せたら、買ってくれた。この本をこの世で初めて買ってくれた。私もまたこの本を初めて売った本屋になれた(ほかの書店にはこのあと納品に行くところだった)。
そのあとも入荷を知った人が来ては「おめでとう」と言いながらご祝儀がてら買ってくれる。さらにはお花までもらった。この感じ、なつかしい。そう、店を始めた日と同じだ。喜びよりも不安のほうが大きくてうつむいていても、まわりが盛り立ててくれて、なんとか元気を出せた。
開店した日はフワフワと落ち着かなかったのも、一週間もたてばなじんだ。この本が積み上がる風景にも、慣れるのだろうか。一日限りのイベントとも月刊誌に記事が載るのとも違う、これからしばらく続いていく日常が、また新しく始まった。