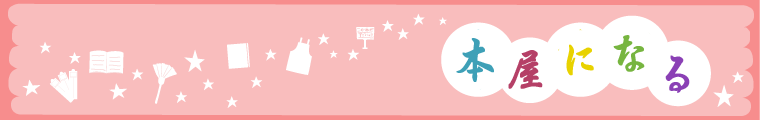本屋になる
第3回 本を読む
本屋さんは店番しながら本が読めるからいいね、と言われたら、今までは怒って言い返していた。読むひまなんてありませんよ、納品と注文と接客に忙しくて、帯を読むだけで精一杯ですよ。
今は、そうなんです、本ばかり読んでいるんです、と半ば申し訳ないような気持ちで答える。
新刊が自動的に送り込まれることもなく、お客様も数えるほどしか来ない古本屋では、誰かが来るのをひたすら待つのが仕事である。そのあいだに棚を整理したり本を磨いたりネットに出品したりすればいいのだけれど、もちろんするのだけれど、ふっと疲れると手近な本に手を伸ばし、読みはじめる。
最初は「仕事中にこんなことをして」という罪悪感があった。でも、店員がパソコンに向かってぼんやりYouTubeを見ているよりは、本を読んでいるほうが傍目にもいいのではないだろうか。本屋なのだから、率先して読む。道を通る人たちの目の前で読み続ける。話し声や商店街のBGMも慣れれば気にならず、
「ご精が出ますね」
と常連のお客様に声をかけられてはっと顔を上げることもしばしばである。
店の本を読んだこともあるけれど、これはやはりお客様に申し訳ないので、自分の本を持ってくる。古本屋を始めてしばらくは売るための本ばかり買っていたのが、年が明けてようやく自分で読む本を買う気分になってきた。
『わたしの小さな古本屋』(田中美穂、洋泉社、2012年2月)は、発売を知ってずっと楽しみにしていた。
著者の田中さんは1994年に倉敷の古本屋「蟲文庫」を始めた、「女子の古本屋」の先駆けのような方である。お店は大原美術館にも近い美観地区のなかの町屋で、老舗のような貫禄がある。4年前にお邪魔したときはどぎまぎして何も買えなかった。この本も、私のような新参者が読ませていただいていいのかしら……と、おそるおそる読み始めた。
苔や亀を愛し、20年近くもひとりでお店を続ける田中さんはピシッと一本気でわが道を歩んでいるのかと思いきやそんなことはなくて、迷ったり怖気づいたりしながら日々を重ねてきたのだとわかった。
静かな街のなかで優雅に営業されているように見えたのも、「お客さんも、近所の常連さんと、遠方からの観光客が半々くらい」で、実は私のところと同じ「観光地の古本屋」だった。店や店主の自分やお客様にまで勝手にカメラを向けられたり、「喫茶コーナーをつくるべきだ」と訴えられたりというのは私にも覚えのあることで、
「本が好きだというだけで古本屋になったわたしには苦痛でしかありませんが、ただ、裏返せば、これは、古本屋の持つ独特の入りにくさがない、ということでもあるのでしょう」
とあるのにしみじみとうなずく。
ライブや展覧会をどんどん開催し、苔の本まで書いて注目されても、
「この店は、実は、たいしてなにもないところなのです。だから、かえってなんでもできる」
と謙虚におっしゃる。こんなふうにできることを地道に積み重ねながら、長く店をやっていけたらと思う。
同じころに出た『きなりの雲』(石田千、講談社、2012年1月)は、第146回芥川賞の候補になった。派手なあおり文句は似合わない、ひっそりとした小説である。
主人公のさみ子は糸の問屋を退職して編みもの教室の先生をしている。元上司の夫婦は新潟で雑貨と洋服の店を切り盛りし、元恋人のじろうくんはCDの販売会社をやめてレコード屋を始めるところ。いわば独立開業の小説だけれど、「食べていければじゅうぶんで、もうけることとはちょっと違う」。お互い少しずつ手を貸しあいながら、それぞれにやっている。
さみ子たちは、仕事も恋愛もふらふらとしてたよりない。就職して結婚して子育てしている人たちからは後ろ指をさされるかもしれない。それでも自分でやってみて、どうなるか確かめていく。
「潮どきは、面とむかって問いつめたり、白か黒かの決意をするより、ふとしたときにたどりつくほうが、悔いがない。」
「歳月の積みかさねが、ひとつの店になっている。」
なんでもないようなフレーズが胸に残る。
こうして本を読むことができる毎日が、何よりもありがたい。
今は、そうなんです、本ばかり読んでいるんです、と半ば申し訳ないような気持ちで答える。
新刊が自動的に送り込まれることもなく、お客様も数えるほどしか来ない古本屋では、誰かが来るのをひたすら待つのが仕事である。そのあいだに棚を整理したり本を磨いたりネットに出品したりすればいいのだけれど、もちろんするのだけれど、ふっと疲れると手近な本に手を伸ばし、読みはじめる。
最初は「仕事中にこんなことをして」という罪悪感があった。でも、店員がパソコンに向かってぼんやりYouTubeを見ているよりは、本を読んでいるほうが傍目にもいいのではないだろうか。本屋なのだから、率先して読む。道を通る人たちの目の前で読み続ける。話し声や商店街のBGMも慣れれば気にならず、
「ご精が出ますね」
と常連のお客様に声をかけられてはっと顔を上げることもしばしばである。
店の本を読んだこともあるけれど、これはやはりお客様に申し訳ないので、自分の本を持ってくる。古本屋を始めてしばらくは売るための本ばかり買っていたのが、年が明けてようやく自分で読む本を買う気分になってきた。
『わたしの小さな古本屋』(田中美穂、洋泉社、2012年2月)は、発売を知ってずっと楽しみにしていた。
著者の田中さんは1994年に倉敷の古本屋「蟲文庫」を始めた、「女子の古本屋」の先駆けのような方である。お店は大原美術館にも近い美観地区のなかの町屋で、老舗のような貫禄がある。4年前にお邪魔したときはどぎまぎして何も買えなかった。この本も、私のような新参者が読ませていただいていいのかしら……と、おそるおそる読み始めた。
苔や亀を愛し、20年近くもひとりでお店を続ける田中さんはピシッと一本気でわが道を歩んでいるのかと思いきやそんなことはなくて、迷ったり怖気づいたりしながら日々を重ねてきたのだとわかった。
静かな街のなかで優雅に営業されているように見えたのも、「お客さんも、近所の常連さんと、遠方からの観光客が半々くらい」で、実は私のところと同じ「観光地の古本屋」だった。店や店主の自分やお客様にまで勝手にカメラを向けられたり、「喫茶コーナーをつくるべきだ」と訴えられたりというのは私にも覚えのあることで、
「本が好きだというだけで古本屋になったわたしには苦痛でしかありませんが、ただ、裏返せば、これは、古本屋の持つ独特の入りにくさがない、ということでもあるのでしょう」
とあるのにしみじみとうなずく。
ライブや展覧会をどんどん開催し、苔の本まで書いて注目されても、
「この店は、実は、たいしてなにもないところなのです。だから、かえってなんでもできる」
と謙虚におっしゃる。こんなふうにできることを地道に積み重ねながら、長く店をやっていけたらと思う。
同じころに出た『きなりの雲』(石田千、講談社、2012年1月)は、第146回芥川賞の候補になった。派手なあおり文句は似合わない、ひっそりとした小説である。
主人公のさみ子は糸の問屋を退職して編みもの教室の先生をしている。元上司の夫婦は新潟で雑貨と洋服の店を切り盛りし、元恋人のじろうくんはCDの販売会社をやめてレコード屋を始めるところ。いわば独立開業の小説だけれど、「食べていければじゅうぶんで、もうけることとはちょっと違う」。お互い少しずつ手を貸しあいながら、それぞれにやっている。
さみ子たちは、仕事も恋愛もふらふらとしてたよりない。就職して結婚して子育てしている人たちからは後ろ指をさされるかもしれない。それでも自分でやってみて、どうなるか確かめていく。
「潮どきは、面とむかって問いつめたり、白か黒かの決意をするより、ふとしたときにたどりつくほうが、悔いがない。」
「歳月の積みかさねが、ひとつの店になっている。」
なんでもないようなフレーズが胸に残る。
こうして本を読むことができる毎日が、何よりもありがたい。