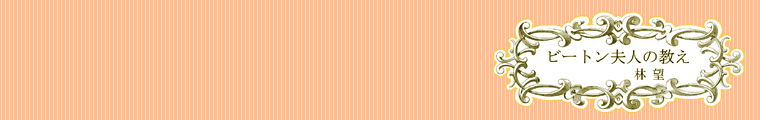ビートン夫人の教え
3 <前編>
イザベラ・ビートンという人がこの本で大成功を収めた理由の一つは、この本を貫く原理が決して高踏的抽象論ではなくて、あくまでも現実主義の、穏健な低い目線を持っていたことであったに違いない。
人付き合いや召使いとの接しかたを説諭したついでに、彼女は服装の原理や注意点に触れてもいる。それが、ある意味ではとても保守的で地道なのが、なにか千古不易の道理を教えているように読める。曰く、
「洋品を買うについては、シルクのドレスであれ、ボンネット、ショール、あるいはリボンであれ、次の3点に留意すべきである。
産業革命の果実として、新しく中産階級が成立してきた当時のイギリス社会にあって、その中産階級的モラルとはなにかということを模索していた人たちには、こうしたビートン夫人の教えは、きっとなんだかほっとするものと感じられて、抵抗無く受け入れられたものと思われ、従ってまた、彼らの堅実な生活モラルに大きな根拠を与えてくれたのでもあろう。
彼女は、自分自身が、以前『Englishwoman’s Domestic Magazine』の8巻に書いたことを、あたかも誰か他に執筆者がいるような口ぶりで引用しているのであるが、そこには次のように書かれている。
「誰がなんと言おうと、書こうと、演説しようと、また皮肉ろうとも、これだけは確かなことである。すなわち、流行のモードというものは、どれも似たり寄ったりで、ばからしく大げさなデザインであったとしても、誰もそれをおかしいとは思わないだろうし、にもかかわらず、実際に普通の人々が日常に身につけて便利に心地よく着ている服装は、そうした流行物とは正反対のデザインになっているということである」
まるで今日ただいまの、あのアホらしいブランド狂奔の風潮について書かれたのではないかと思うくらい、この言う所はまさに正鵠を射ているといわねばなるまい。私自身もこういうところを読むと、あの兼好法師がいったように、「見ぬ世の友」に逢うた心地がするというものである。
こういう堅実で市民的な考え方から、イザベラはまた、チャリティということについても、それが家庭を主宰する者としての義務であるという立場から一言述べている。
思えば、ヴィクトリア時代は、新たに富を手にした中産階級の人達が、チャリティという形で自ら社会の変革や改良に参画し始めた時代でもあった。
1895年にオクタヴィア・ヒル女史、ロバート・ハンター卿、H・D・ローンズリー修道士の三名によって樹立されたナショナル・トラストや、エベネザー・ハワードによって主唱され、二十世紀になってから具体的な実現を見た田園都市構想など、いずれもヴィクトリア時代の啓蒙的社会改良主義と市民の自律とが結実した結果であった。同じ時代を生きたビートン夫妻もまた、こうしたチャリティによる社会貢献という風潮の影響を受けたものと思われる。
ここで彼女が使っている「Charity and benevolence」という言葉はいずれも日本語には等価の表現がなく、まことに訳しにくい言葉であるが、チャリティもベネヴォレンスも似たような概念で、本来的にはキリスト教的な慈愛の心、善意を以て、他者を助ける営為のことであるが、現代普通の言葉としては、どちらかというとチャリティのほうが広く使われてより公利公益的な意識が強く、ベネヴォレンスのほうは、やや慈恵慈愛という善意行動的な傾きがあるかもしれない。
これらについて彼女が「必ずしも他人の為ではなく、むしろ自分自身の為にするのである」と言っているのは、イギリスにおけるチャリティの精神を理解する上で、非常に大切なところである。
また、こうも言っている。
「この場合、収入が少ないとしても、世に言う『貧者の一灯』式に、分相応の貢献をすることができるはずである。そしてよく記銘しておくべきことは、そうした社会的貢献を価値あらしめるものは、その金額の多寡ではなくして、チャリティの精神そのものであるということである。この精神こそは、かかる貢献のもっとも嘉すべき部分なのである」
まさに、ナショナル・トラストなどは、そういう貧者の一灯を膨大に募って成り立っているチャリティなのであった。
単なる家事家政のみに留まらず、こうした社会的視野にまで及ぶところが、ビートン夫人の家政書の特色で、そこには、夫サミュエルの開明主義者としての意志なども反映しているのかもしれない。
ここでもイザベラはウイリアム・カウパーの詩句を引用している。
まことのチャリティは
見事に仕立てられた樹のようなものだ。
愛を肥料としてまず芽吹く
希望によって成長し、乱暴に扱えば
荒れるけれど、それでもまた褪せぬ緑を芽吹かせる
そして豊潤なる緑陰を成し
果実は地に落ち、枝は亭々と天を指す
ただ、ここで彼女は、家庭婦人の社会貢献の具体的な一法として、田園地域の貧しい人々の家を訪問して、衛生、勤勉、料理、あるいは家庭管理のあれこれをアドバイスするということを勧めているのだが、はたしてそういうことが実際に実現可能であったかどうか、ちょっとなんともいえない。
次に買い物について、ということにも一言及ぼしている。彼女の買い物の原則は「値段が安いものが良いものだ、ということを原理とせよ」ということで、これまさに、一円二円の安きを選んでスーパーを歩き回る現代日本の主婦たちの気持ちを代弁しているようなところがある。上げ潮の中産階級にあって、しかも、出版業で成功を収めつつあった若き経営者サミュエルの妻であった彼女が、敢てこういうことを主張しているのは、半分は華奢に流れようとする自分への戒めであったようにも読める。
そして、できれば買い物は主婦が自分でマーケットに行って買うことを勧め、足まめに買い物をして回ることから、魚肉等の善し悪しを見定める眼識を得ると言っていること、それから、買い物をしたら、巨細漏らさずそれを当日に家計簿に書き入れ、なお月末ごとにその〆めをして、赤字経営に陥るのを防ぐべしと教えている。
いずれも、じつにもっともであって、一種のバブル時代でもあったヴィクトリア時代にあっては、こういう真面目な日常へのアドバイスはなかんずく大切なものであったろうかと想像される。
いっぽうまた、現代と当時とで大きく違っていたのは、家庭内に人を雇うということである。
本書のなかで、イザベラは、どのようにして人を雇うべきか、人を雇う場合の留意点、また、主人として、使用人たちに対する態度や考え方をどう見るべきか、というような諸点について詳細に述べているのだが、そういうことは現代の我々には、あまり関係がないので、ここでは詳しく書かないことにする。
しかしながら、当時の「中産階級」というものが、じっさいにどのくらいの収入を得ていたのか、またそれぞれの収入に応じて、どういう人達を雇うのが適正規模と考えられていたか、また彼ら使用人たちの給与はどんなものであったかというようなことが書かれているのは、それなりに興味深い。
しこうして、こういうデータを知ることは案外と簡単でないので、ここに書かれていることを、ちょっとだけ紹介しておくことにしたい。そうすると、『日の名残り』や『ハワーズエンド』などのイギリス映画を見る時にも、なにがしかの参考になるかもしれない。
さて、オックスフォード版の原書に付せられた注釈によると、名実ともに中産階級になったということのできる境界線は、年収300ポンドというところにあったという。じっさいには、100ポンドくらいでも中産階級と言う場合もあり、1000ポンドでもなお中産階級にとどまるというふうにかなりの幅があったらしい。
そうして、1867年における平均的な中産階級の年収は154ポンドであったとF.クルーゼットの『ヴィクトリア時代の経済』という本に書いてあるそうである。
使用人のほうについては、男の使用人の最高地位たる家令(House Steward)でも年収は80ポンドに留まり、一番低額の少年厩務員ともなると、わずかに6ポンドというのだから、まことに安いものだったようである。また女の使用人の場合は最高でも女中頭(House keeper)の45ポンドであり、最低の皿洗いの少女ではたったの4ポンドで一年働いたのであった。
逆に言えば、それだけ安い費用で人が雇えたからこそ、中産階級以上の家庭では、潤沢に人手を確保できたのだともいえる。そこで、年収別の使用人の適正規模は次のとおりだという。
£1,000:料理人、上級ハウスメイド、子守、下級ハウスメイド、男性の召使
£750:料理人、ハウスメイド、子守、近習(footboy)、
£500:料理人、ハウスメイド、子守
£300:一般メイド、子守
£200〜£150:一般メイド(と少女を時々雇う)
こうして、新しく中産階級に参入してきた家々では、どうやって使用人を雇い、どのように接したら良いか、またその給料をどう見積もったら良いかということについての適切なアドバイスを求めていたのであるから、まさにこの時代に、こういう本が出たことは、時宜にかなったものであったことは疑いない。
単なる料理書でなくて、こんなところまで広く視野を及ぼしてたっぷりと情報を教諭し、かつそれについての古典的教養までも与えようとしたのは、編集者としてのサミュエルの非凡な才覚を証明するものではないかと思われるのである。
(後編につづく)
人付き合いや召使いとの接しかたを説諭したついでに、彼女は服装の原理や注意点に触れてもいる。それが、ある意味ではとても保守的で地道なのが、なにか千古不易の道理を教えているように読める。曰く、
「洋品を買うについては、シルクのドレスであれ、ボンネット、ショール、あるいはリボンであれ、次の3点に留意すべきである。
- 自分の収入に対して高すぎないこと、
- 品物の色が自分の肌の色にマッチし、サイズや柄が体の大きさにマッチしていること、
- その色が他に持っている服とマッチすること」
産業革命の果実として、新しく中産階級が成立してきた当時のイギリス社会にあって、その中産階級的モラルとはなにかということを模索していた人たちには、こうしたビートン夫人の教えは、きっとなんだかほっとするものと感じられて、抵抗無く受け入れられたものと思われ、従ってまた、彼らの堅実な生活モラルに大きな根拠を与えてくれたのでもあろう。
彼女は、自分自身が、以前『Englishwoman’s Domestic Magazine』の8巻に書いたことを、あたかも誰か他に執筆者がいるような口ぶりで引用しているのであるが、そこには次のように書かれている。
「誰がなんと言おうと、書こうと、演説しようと、また皮肉ろうとも、これだけは確かなことである。すなわち、流行のモードというものは、どれも似たり寄ったりで、ばからしく大げさなデザインであったとしても、誰もそれをおかしいとは思わないだろうし、にもかかわらず、実際に普通の人々が日常に身につけて便利に心地よく着ている服装は、そうした流行物とは正反対のデザインになっているということである」
まるで今日ただいまの、あのアホらしいブランド狂奔の風潮について書かれたのではないかと思うくらい、この言う所はまさに正鵠を射ているといわねばなるまい。私自身もこういうところを読むと、あの兼好法師がいったように、「見ぬ世の友」に逢うた心地がするというものである。
こういう堅実で市民的な考え方から、イザベラはまた、チャリティということについても、それが家庭を主宰する者としての義務であるという立場から一言述べている。
思えば、ヴィクトリア時代は、新たに富を手にした中産階級の人達が、チャリティという形で自ら社会の変革や改良に参画し始めた時代でもあった。
1895年にオクタヴィア・ヒル女史、ロバート・ハンター卿、H・D・ローンズリー修道士の三名によって樹立されたナショナル・トラストや、エベネザー・ハワードによって主唱され、二十世紀になってから具体的な実現を見た田園都市構想など、いずれもヴィクトリア時代の啓蒙的社会改良主義と市民の自律とが結実した結果であった。同じ時代を生きたビートン夫妻もまた、こうしたチャリティによる社会貢献という風潮の影響を受けたものと思われる。
ここで彼女が使っている「Charity and benevolence」という言葉はいずれも日本語には等価の表現がなく、まことに訳しにくい言葉であるが、チャリティもベネヴォレンスも似たような概念で、本来的にはキリスト教的な慈愛の心、善意を以て、他者を助ける営為のことであるが、現代普通の言葉としては、どちらかというとチャリティのほうが広く使われてより公利公益的な意識が強く、ベネヴォレンスのほうは、やや慈恵慈愛という善意行動的な傾きがあるかもしれない。
これらについて彼女が「必ずしも他人の為ではなく、むしろ自分自身の為にするのである」と言っているのは、イギリスにおけるチャリティの精神を理解する上で、非常に大切なところである。
また、こうも言っている。
「この場合、収入が少ないとしても、世に言う『貧者の一灯』式に、分相応の貢献をすることができるはずである。そしてよく記銘しておくべきことは、そうした社会的貢献を価値あらしめるものは、その金額の多寡ではなくして、チャリティの精神そのものであるということである。この精神こそは、かかる貢献のもっとも嘉すべき部分なのである」
まさに、ナショナル・トラストなどは、そういう貧者の一灯を膨大に募って成り立っているチャリティなのであった。
単なる家事家政のみに留まらず、こうした社会的視野にまで及ぶところが、ビートン夫人の家政書の特色で、そこには、夫サミュエルの開明主義者としての意志なども反映しているのかもしれない。
ここでもイザベラはウイリアム・カウパーの詩句を引用している。
まことのチャリティは
見事に仕立てられた樹のようなものだ。
愛を肥料としてまず芽吹く
希望によって成長し、乱暴に扱えば
荒れるけれど、それでもまた褪せぬ緑を芽吹かせる
そして豊潤なる緑陰を成し
果実は地に落ち、枝は亭々と天を指す
ただ、ここで彼女は、家庭婦人の社会貢献の具体的な一法として、田園地域の貧しい人々の家を訪問して、衛生、勤勉、料理、あるいは家庭管理のあれこれをアドバイスするということを勧めているのだが、はたしてそういうことが実際に実現可能であったかどうか、ちょっとなんともいえない。
次に買い物について、ということにも一言及ぼしている。彼女の買い物の原則は「値段が安いものが良いものだ、ということを原理とせよ」ということで、これまさに、一円二円の安きを選んでスーパーを歩き回る現代日本の主婦たちの気持ちを代弁しているようなところがある。上げ潮の中産階級にあって、しかも、出版業で成功を収めつつあった若き経営者サミュエルの妻であった彼女が、敢てこういうことを主張しているのは、半分は華奢に流れようとする自分への戒めであったようにも読める。
そして、できれば買い物は主婦が自分でマーケットに行って買うことを勧め、足まめに買い物をして回ることから、魚肉等の善し悪しを見定める眼識を得ると言っていること、それから、買い物をしたら、巨細漏らさずそれを当日に家計簿に書き入れ、なお月末ごとにその〆めをして、赤字経営に陥るのを防ぐべしと教えている。
いずれも、じつにもっともであって、一種のバブル時代でもあったヴィクトリア時代にあっては、こういう真面目な日常へのアドバイスはなかんずく大切なものであったろうかと想像される。
いっぽうまた、現代と当時とで大きく違っていたのは、家庭内に人を雇うということである。
本書のなかで、イザベラは、どのようにして人を雇うべきか、人を雇う場合の留意点、また、主人として、使用人たちに対する態度や考え方をどう見るべきか、というような諸点について詳細に述べているのだが、そういうことは現代の我々には、あまり関係がないので、ここでは詳しく書かないことにする。
しかしながら、当時の「中産階級」というものが、じっさいにどのくらいの収入を得ていたのか、またそれぞれの収入に応じて、どういう人達を雇うのが適正規模と考えられていたか、また彼ら使用人たちの給与はどんなものであったかというようなことが書かれているのは、それなりに興味深い。
しこうして、こういうデータを知ることは案外と簡単でないので、ここに書かれていることを、ちょっとだけ紹介しておくことにしたい。そうすると、『日の名残り』や『ハワーズエンド』などのイギリス映画を見る時にも、なにがしかの参考になるかもしれない。
さて、オックスフォード版の原書に付せられた注釈によると、名実ともに中産階級になったということのできる境界線は、年収300ポンドというところにあったという。じっさいには、100ポンドくらいでも中産階級と言う場合もあり、1000ポンドでもなお中産階級にとどまるというふうにかなりの幅があったらしい。
そうして、1867年における平均的な中産階級の年収は154ポンドであったとF.クルーゼットの『ヴィクトリア時代の経済』という本に書いてあるそうである。
使用人のほうについては、男の使用人の最高地位たる家令(House Steward)でも年収は80ポンドに留まり、一番低額の少年厩務員ともなると、わずかに6ポンドというのだから、まことに安いものだったようである。また女の使用人の場合は最高でも女中頭(House keeper)の45ポンドであり、最低の皿洗いの少女ではたったの4ポンドで一年働いたのであった。
逆に言えば、それだけ安い費用で人が雇えたからこそ、中産階級以上の家庭では、潤沢に人手を確保できたのだともいえる。そこで、年収別の使用人の適正規模は次のとおりだという。
£1,000:料理人、上級ハウスメイド、子守、下級ハウスメイド、男性の召使
£750:料理人、ハウスメイド、子守、近習(footboy)、
£500:料理人、ハウスメイド、子守
£300:一般メイド、子守
£200〜£150:一般メイド(と少女を時々雇う)
こうして、新しく中産階級に参入してきた家々では、どうやって使用人を雇い、どのように接したら良いか、またその給料をどう見積もったら良いかということについての適切なアドバイスを求めていたのであるから、まさにこの時代に、こういう本が出たことは、時宜にかなったものであったことは疑いない。
単なる料理書でなくて、こんなところまで広く視野を及ぼしてたっぷりと情報を教諭し、かつそれについての古典的教養までも与えようとしたのは、編集者としてのサミュエルの非凡な才覚を証明するものではないかと思われるのである。
(後編につづく)