おすすめマンガ時評『此れ読まずにナニを読む?』
第88回 岡本健太郎『山賊ダイアリー』(講談社)
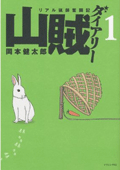
(c) 岡本健太郎/講談社 既刊1巻
かく言う私は、ほんの1年くらいに前に、知人が使っていて知った言葉だ。ジビエとは、狩猟によって捕獲された野性の鳥獣、といった意味合いのようである。つまり牛や豚、ニワトリといった家畜ではなく、野山の野性の鳥や獣たちをさす言葉のようなのだ。
多くの人にとってはあまり日常的ではないだろう「ジビエ」。本作の作者は、そんなジビエ料理を頻繁に楽しんでいる。それも、自分で狩ってきた獲物で。
そう、作者はなんと現役の「猟師」なのである。
友達の家まで片道で7kmぐらいあるという田舎に生まれた作者は、子供の頃から近所の猟師のおじいさんが遊び相手で、大人になるというのは猟師になることだと思っていたという。
東京に住んでいたこともある彼だが、故郷の岡山で銃や罠の免許を取得し、猟をする。
本作は、彼の猟師生活を、つまり、ウサギ、ハト、ヘビ、カラス、カモ……とさまざまな動物を狩り、そしてそれらを食べる様子を綴ったマンガなのだ。
猟の様子だけでなく、狩猟免許の種類や、猟の手順や道具についての話も興味深い。銃といっても散弾銃と空気銃という選択肢がある、とか、散弾銃はしとめた獲物に弾丸が入ってしまうので食べづらくなる、とか、銃器類に興味のない私は考えたこともなかった、でも聞いてみると「なるほど」と思う話がいろいろ出てくる(作者は空気銃を選択)。
だが、本作で一番衝撃的だったのは、猟師である作者が、思いがけない生き物を狩り、食べることだ。
ウサギ、ハト、カモは「ほほぅ」という感じだが、形も生々しいヘビにいたっては「ヘ…ヘビか……」とたじろいでしまったものの、まぁ聞かない話ではない。でもカラスを食べてみる、というのには心底ビックリした。
農家の方にカラス退治を依頼された作者は、「カラスはどんな味なのか?」と、食べたことがある先輩猟師のアドバイスを参考に、焼き鳥にして食べてみるのだ。すると、色こそ黒っぽいものの胸肉はクセがなく「脂の無い牛肉のよう」で歯ごたえがしっかりしていてなかなかいける、という。
そうか、作者にとって、カラスは「食べられる」生き物なのだ。
…へぇ!
その発想はなかったなぁ、である。
たとえば、作者と私が同じ光景を見たとする。その画像をモニターに映し出し、お互いが「食べられると認識してるもの」を(なんでもいいけど)仮に赤で表示するとしたら、そこにカラスやヘビが含まれていたら、私にとっては「食べられる色」はつかないけれど、作者にとっては多分はっきりと「赤」で表示されるだろう。ウサギだと、これは私にとっては微妙で、「食べたことはあるけれど、即、食べることは思い浮かばない」ラインかもしれない。とすると、「私ビジョン」での表示は、まあ、うすいピンクくらいだろうか。って、そんな「仮定の色分け」を厳密にしてもしようがないわけだが、なにが言いたいかというと、「作者にとって、世界は私とは違って見えている」んだなあ、と衝撃を受けた、という話なのだ。
食べる肉と言えばもっぱら「店で買ってくる」のが一般的な都市生活者にとっては、「獲物を捕る」→「解体する」という普段目にしない工程は、大変「非日常的」に見える行為だ。でも、猟師といっても、作者も現代の若者なので、住んでいるのはマンションだ。ハトやカモの毛をむしるのはベランダで、焼くのはごくごく一般的なガスコンロのグリルだったりする。つまり、猟→解体以降の、調理や食事の場面はまったく私たちの日常と地続きなのだ。だからこそ作者の「猟」が身近に感じられるのかもしれない。
初めてハトを撃ち落としたとき、作者は考える。
「普段から肉は食べているわけで、ぼくが知らない所で生き物は死んでいるわけですが、それを自分の手で行うというのはやはり複雑なものがあります」(1巻p.22)
自分が知らない所で生き物が死んでいる、いう部分は、都市生活者の大半は、同じ感覚だろう。だが、ハトを自分の手で解体し、タレに浸けガスコンロのグリルで焼いて食べた後、作者は、
「自分が自然の生態系の中に組み込まれたような感覚になります……」というのだ(1巻p.26)。
たしかに、「獲物を捕る」ところから「料理して食べる」までのサイクルを体験することは、「命をいただく」ことをリアルに体感することに他ならない体験だと思う。
通常は、肉と言えば「買ってくるもの」で、食材となる前に「生きていた」ことに思いをはせることはあまりなくなってしまっている私も、本作のこのくだりには、自分が「食物連鎖の一角を担う生き物」であることに改めて気がつかされたのだった(作者の考える生態系だと、人間は一番上じゃなくて「クマ」「イノシシ、キツネ」の次点くらい…というのも、なんだか面白い。人間は丸腰ではかなり弱いけど、発達した脳と器用な手先で作り出した銃をはじめとする「道具」のおかげで生態系のなかですごい「下克上」を果たしてるんだよなあ…と感じてしまった)。
おまけとして1巻の最後に、作者が禁猟期に近所の川で、天然うなぎを釣って料理して食べる話がある。脂っぽい養殖ものとはまったく違う魚本来の味わい、という天然ウナギはすごく美味しそうなのだが、でもよくよく考えてみれば、私自身の「ウナギはOK」でも「ヘビは食べられない、食べたくない」という「感覚」には、実は合理的な説明はないのかもしれない、と思い至った(ヘビとうなぎ、見た目は似てるし)。
つまりそれは「幻想」というか、自分が生きてきた範囲で目にした文化の中での「これは食べられる」「これは食べられない」という刷り込みであって、根拠は実はあんまり明確ではないのかもしれない、と思ったのだ。
そう考えてくると、ふと、自分の中の「これは食べられる」ラインがゆらいできそうな気になってくる。これまで水族館でイワシやアジを「美味しそう……」と妙に熱のこもった目で見てしまうことはあったが、正直、ウサギやハトにはそういう自分内の「食べたい」センサーは働かなかった。
カラスにいたっては、妙にものおじせずベランダやゴミに近づいてくるカラスを苦々しく思うだけだったのに、本書を読んだいまでは、無意識に「…こいつ、食べられるのか……」と不穏な目つきでじ――っと凝視してしまいそうでコワい(さすがにヘビに食欲を感じるのはまだ難しそうだが)。
猟師である作者は、自分の手で殺した獲物は回収する義務がある、と、池に浮かぶしとめたカモを、11月の気温3度のなか、裸で池に入って(読んでるだけで凍えそうなくらい寒そうだ)もちかえる。食べるための肉といえばスーパーか精肉店か、とにかく「店で買ってくる」都市生活者にとっては、つい薄れがちな「命をいただく」感覚。逆接的だが、動物を直接狩る猟師の作者は、それを強烈に感じ、大切にしているように思える。
実は本作の冒頭で、もっとも思いがけないものを作者は食べてみせる。「山で遭難したらぜひ 思い出してみてください」ということだが、実行できるかどうかはともかく、本作は、「食べる」ことに関してさまざまな見方を教えてくれるエッセイマンガなのだ。
(川原和子)
