おすすめマンガ時評『此れ読まずにナニを読む?』
第55回 『乙嫁語り』 森薫 エンターブレイン
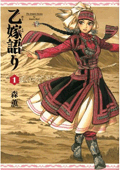
(C)森薫/エンターブレイン
カルルクの両親、祖父や祖母、姉夫婦とその子どもたち……と、大家族のエイホン家の「嫁」になったアミル。山の向こうからやってきたアミルのもちこんだ衣装や狩りの道具などは、エイホン一族にとってはちょっとした異文化だ。とまどいながらも好意的にうけとめ、アミルを受け入れていくあたたかなエイホン家の人たち。最初はぎこちないが、夫婦として少しずつ距離を縮めていくアミルとカルルクだったが、一方、アミルの実家では、嫁ぎ先で死んでしまったアミルの妹の代わりに、アミルを取り返して再び嫁がせよう、というきなくさい策略が動き始めていた……。
本作でまず目をひかれるのが、画面のとにかく細かい描き込みっぷりだ。アミルの着ている服やアクセサリーから壁掛けやじゅうたんにいたるまで、細かな模様(刺繍)までとてもていねいに描かれていて、そのあまりの細密な描写に圧倒されてしまう。
だがマンガというのは不思議なもので、これだけ細かい描き込みがあると、得てしてコマあたりの情報量が「重く」感じて読みづらくなってしまい、かえって読者をはじいてしまうこともあるように思う。しかし、本作の描き込みは、少なくとも私にとってはむしろ作品にひきこまれる要因になっているのだ。それはひょっとしたら、本作の、手描きならではのあたたかみが感じられる描き込みっぷりには、作者の「これを描くのが、好きでたまらない」という愛がひしひしと感じられるせいかもしれない。
第2話では、大工のおじさんに憧れる幼い少年・ロステム(カルルクの末の甥っ子)が、大工の見事な細工の腕前にみとれてしまう様子がていねいに描かれる。読者である私たちもロステムの目を通して、人の手によって素晴らしい細工が作られていく様子にひきこまれてしまうのだ。同じ話のなかに新婚のアミルとカルルクが壁掛けを色あわせをみながら替えていくシーンもあるが、その壁掛けも彼らや親族の手作りであることが示される。その描写は、生活の中の必要なものたちが、生活している人自身の手で作られていて、しかもそれらが非常に美しいということを祝福しているかのようだ。
そして、ヒロインのアミル。作者があとがきで「中央アジアならではのものにしたいなあと思ってこうなった」という彼女は、作者曰く「野性」「天然」「強い」「でも乙女」「でもお嬢様」と、一見矛盾しそうな要素をあわせもつ女性だ。ふだんはおっとりと優しいが、弓をあやつり馬上からウサギを見事に射止め、手際よくさばいて狩りをしないエイホン家の人にウサギ料理をふるまうワイルドな人物でもある。
また、アミルは結婚したときに、姑であるカルルクの母から布と糸をもらい、それらと自ら狩ったウサギの皮とで夫・カルルクの服を作るが、実はその布と糸は、アミルの服を作ってはどうか、という意味でくれたものだったのだ。それをカルルクの母から聞いたアミルは、自分が汚れていると遠回しに言われたのでは、と勘違いして急に服を脱ぎ「洗ってきます!!」と下着姿になって周囲をあわてさせる「天然」でもある。それでいて、基本的に人の善意を疑わないおおらかなかんじや、いったんダメ、と言ったらダメですよ、とにっこり笑って曲げないところには、彼女のお嬢さんぽい育ちの良さが感じられる。
そんな妻に対し、まだ見た目に幼さの残る12歳の夫・カルルクは、とまどいながらも要所では凛々しく「夫らしい」ところを見せる。あるときカルルクとアミルは遊牧民族のおじに届け物がてら結婚の挨拶をしに行く。おじやその一族に歓待を受けながらも、カルルクは、妻の方が8歳も年上の新しい夫婦に対する祝福だけではない空気を感じ取る。実際、若夫婦が退席すると、おじ一族の老人は「ずいぶん歳のいった嫁をもらったもんだ」「あれじゃあそう何人も産めないんじゃないか」と辛辣な言葉を口にするのだ。だが、夫婦二人だけになると、カルルクはアミルに「お話があります」と改まって切り出し、「最初に会った時 びっくりしたのは聞いてた話と違ってたからで」と言葉を選びながら、きっぱりとこう言うのだ。「僕はアミルがもっと若かったらとか 全然思ってないからね」。言われたアミルは頬をそめて「…はい」と答える。今の感覚では年齢的には子どもだが、カルルクはとても大事な言葉をきちんと言える人物として描かれているのだ。
作者はあとがきで、本作を「中央アジアの嫁まんがです」と言っている。そう言われてみると、本作には二人の「勇ましい嫁」がいることに気がついた。弓で野性のウサギやキツネを狩るアミルと、そして嫁ぎ先の祖母だ。
カルルクが風邪をひいたとき、アミルは本人が倒れるのでは、と心配されるくらい、つきっきりで夫を看病する。もちろん、まだ少年といっていい夫の病に対する単純に心配な気持ちからくる行動だろうが、単なる風邪と言われているのにこんなに心配してしまうのは、無意識に、夫の存在だけが、アミルがこのなじみの薄い一族のなかにいることを許されている唯一の根拠であると感じているせいかもしれない。このときにアミルをなだめ、眠りにつかせるのが、かつては「嫁」というある種の異物としてこの一族に入ってきた経験をもつであろうカルルクの祖母なのだ。
そんな優しい祖母は、アミル夫婦の留守中に「アミルを返せ」と横暴な態度でやってきたアミルの実家の一族に対して、ウチの嫁は渡さない、と、自分の嫁入り道具だった年代物の弓(!!)をつかって撃退する強い大ベテランの「嫁」でもあるのだ。
アミルは、一族の都合で、一度も会ったことのない相手のところ(しかも、大家族のもと)に嫁ぐ。
アミルたちのくらしは、現代の日本ではなかなか考えづらいシチュエーションだし、どちらかといえば「個人の意志を無視した因習」として否定的にとらえられそうな状況だ。にもかかわらず、読んでいて嫌な気持ちにならないのは、エイホン家の人々が、アミルのもちこむ自分たちにはなじみのうすくなった習慣も否定せず、おおらかに受け入れる品のよい人々だからだろう。エイホン家の人々のアミルに対する態度には、一族の一員として迎え入れたからには大事にする、という覚悟が感じられる。現実にはなかなか難しいことだと思えるが、ここで描かれる「抑圧的ではない大家族」は、いざという時には結束して外敵から自分たちを守る、現代では見かけることの少なくなった「強い絆をもった共同体」でもあるのだ。
本作では、アミルの内面描写やモノローグは描かれない。全体に、言葉はどちらかというと少なめなのだが、一方「画面」は、とても饒舌だ。本作の描き込みは細かいけれど、むやみな描き込みではなく、マンガとしての「ここのシーンでは、これを見せたい」という意図を邪魔しないように描かれているから、描き込みがうるさくなく、むしろ気持ちがよいのだと思う。
「乙嫁語り」は『フェローズ』という隔月刊誌に連載されている。コンビニなどでは手に入らないし、かなりディープなマンガ読みを対象にした雑誌、という印象だ。一言で言うとマニアックなわけだが、そこに連載された本作は、マニアックな読者のニーズも満たしつつ、実は、かなり幅広い読者に受け入れられる作品なのでは、と感じられるのだ(実際、ネット書店のアマゾンでのレビューには、娘時代以来、マンガを読まなくなって久しい還暦を過ぎた母親が老眼鏡をかけて夢中で読んでいる、という読者の書評も投稿されている)。 細部までマニアックに作り込んでいながらも、同時に、作品としては幅広い層をひきつけるメジャーさがある、と思うのだ。
作者が言うように「中央アジアの嫁マンガ」としても読めるし、「シルクロード関連の衣装・風俗マンガ」としても、マニアックな読者の目をも楽しませるだろう。また、「美しい姉さん女房のアミルにときめくマンガ」としても読めるし、「少年であるカルルクの年齢に似合わぬ毅然としたところにドキッとするマンガ」という読み方や「年の差カップルのほのぼのマンガ」としても、「大家族ホームドラマ」としても楽しめる。「マニアックにして、メジャー」な一作、と感じるゆえんである。
早く2巻が出ないかな、と心待ちにしている作品だ。(川原和子)
