おすすめマンガ時評『此れ読まずにナニを読む?』
第17回 『一角散』 津野裕子 (青林工藝舎)
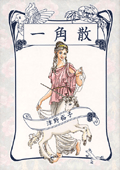
(C) 津野裕子/青林工藝舎
津野裕子は、「ガロ」の作家である。作品はほぼみな短編だ。1986年デビュー以来、単行本は四冊。寡作ながら、独特の絵柄と幻惑的な世界観がとても魅力的だ。簡素な線で描かれる少年少女たちのしなやかに伸びる肢体は、いわゆる「萌え絵」とは違ったやり方ではあるけれど、でも現実の身体と距離をとりつつ、瑞々しい存在感だけは紙面に定着する技という意味では、同時代的な並行性を持っている。少女たちをめぐるエロスという主題が描かかれても、そこにはガラスか真っ白な陶器でつくられたような、冷ややかな清潔さがある。文学性で人気のあるロリコンマンガ家、町田ひらくが影響を受けた作家といえば納得する向きもいるだろうか。だからぼくは、かつて「百合天国」という百合モノのアンソロジーコミックの編集に参加したとき、津野裕子に原稿を依頼しようとひそかに画策もした(残念ながら、休刊のため実現はしなかったけれど)。萌えの文脈でキャラ絵を描いている若いひとなら、きっと反応すると思ったからだ。
津野裕子の魅力は、それだけではない。もうひとつ、比類なき透明感と浮遊感がある。夢を夢のまま描いたかのような、夢と現実の境目がどんどん曖昧になっていくような感覚と、かすかな切なさである。
たとえばこんな調子だ。叔父に借りた本を返しに、森の中の屋敷を訪れた少女は、ギリシャ神話の本を見ているうち、いつの間にかソファで眠っている自分自身の姿を見ることになる。それを見ている自分は、かつて叔父に見せられた写真の少女になっているのだ。しかもその「少女」は女装した少年時代の叔父であり、主人公は「自分」のスカートをめくって確かめてしまう。「暗示に耐えきれず違和感を調べるヘルマプロディテス」と、ナレーションを兼ねた彼女のモノローグが読者に告げる。
これは『エリシクル(錬金薬)』という掌編のほんのさわりだけを(無粋を承知で)素描したものだ。わずか8ぺージのうちに、私たちが感じる「いま、ここ」のリアリティを撹乱する仕掛けが何重にも畳み込まれている。「この私」が、他でもない「この身体」に宿っているという前提がおかされ、作品世界内の「現実」がいったいどの水準にあるのかも定かではなくなってしまう。
『エリシクル』は、シュールレアリストであるマックス・エルンストの『カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢』の一節を意識して描かれたという。つまりヨーロッパの幻想文学の影響下にあるわけだが、『turbidity』や『双生児の窓』、『ジェミニ』といった作品群も、ヨーロッパのどこかの国のように思わせる風景のなかで展開されている。だが、それが果たしてどの時代のどの国か、と詮索しようとすると、途端に目くらましにあう。地中海旅行だの、グリークミソロジーだのといった名前は出てくるけれど、登場人物たちの固有名や、彼らが暮らす土地の名前は一切呼ばれない。これは日本に住む私たちにとって抽象的な、「遠い」場所という修辞であるように読める。この作者独自の透明な浮遊感は、無国籍で、時代もはっきりしない抽象的な舞台との親和性は高い。
一方、『救命一角散』や『トランス・トランス』、『流感の流行り』、『ダム、スワン』といった作品では、対照的に日本の地方の風景がひどく的確に描かれる。海岸の岸壁、木造の古い家、木々や森、川、ダム、変電所・・・・・・といった見慣れたものたちが、とても瑞々しく描かれる。個人的には、こちらのほうがより魅力的だと思う(工場や高圧鉄塔を最も美しく描くマンガ家だと思っている)。これは1994年刊行の単行本『雨宮雪氷』収録作ではさらに顕著で、作者自ら「どこかの地方のかんじが出せたらいいなあ」と言いつつ、「ロケ地/近所ばっか」と語る。その「地元」とは、富山である。海があり、川があり、平野が終わるとすぐに立山連峰という高山地帯がそびえる土地だ。作者にとっての地元でもある身近な場所である。
やけにリアルな風景が描かれても、やはりリアリティを撹乱するような感覚は変わることはない。われわれの日常と地続きであるはずなのに、いつのまにか浮かび上がってしまうような、たとえるならそんな感覚は、「どこ」を描いても同じであるようなのだ。そのため、こと舞台が「富山」であることを感じさせる作品群を通過した後では、おかしなことに、無国籍で抽象的な舞台で描かれているはずの作品ですら、実は富山にある、周囲とは隔絶した不思議な場所なんじゃないかとすら思えてくる。大げさにいえば、日常と空想の地位が逆転するといった感覚だ。
たとえば、魔女である母親に「恋心を失わせる」魔法の薬を飲ませようとして、逆に魔法で小さくされてしまった双子の少女の物語、『ジェミニ』のラスト近くには、「こんな 小さな空港 めずらしい?」「いなか者 だからねぇ」というセリフとともに、小さな空港が出てくる。これなど、もしかしたら富山空港かな、などとつい考えてしまう。行ったことはないけれど、富山空港は神通川の河川敷に滑走路を持つ、ひどくこじんまりした空港なのだそうだ。(伊藤剛)
