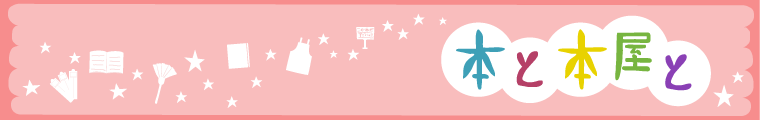本と本屋と
第18回 本屋に積もる
秋のはじめに、歴史書の出版社数十社が主催する研修旅行に参加した。全国から書店の担当者が集まり、名古屋周辺の書店を見学して、どうしたら歴史書が売れるか話しあう。内容の濃い研修に疲れながらも盛り上がり、女子部屋では夜遅くまで書店話が繰り広げられた。(といっても「あの本は判型が大きすぎて困る」「出版社に返品交渉をしたときの忘れられないひとこと」といった瑣末な話に終始した。だって面白いもの)
そこで、あるベテラン書店員さんが
「今の店に異動してきて最初にやったのは書類を捨てること。中をちょっとだけ見て、段ボール3箱くらい捨てました。私はもう開けることないな、と思ったので。何でも捨てちゃうんですよ」
と話していて、ああ、ではぜひ私のところにも来て捨ててください! と、口には出さずに思う。店に残してきた、そして今も増えつつある紙の山が頭をよぎる。
本屋には紙があふれている。売っているのは紙の束だ。その周辺にもブックカバーに袋、本に挟まれたスリップ、検定の申込書、チラシ、お客さま用のご注文伝票、出版社からのFAX・・・・・・ と、ペーパーレス化のレの字もない。
出版社の人からフェアの企画書や売上一覧表をどさりと渡されて、とりあえず箱にしまって、そのまま数年が経過する。たまに思いついたようにまとめて捨ててみるけれど、罪悪感がある(出版社の人に、というより、地球に対して)。かといってコンピュータのデータでもらっても絶対に見ない。注文書だって、その場で「5」とか冊数を書き込んで、番線印(書店の住所印のようなもの)をパンと押してFAXするだけだから気楽に返送できるのであって、メールで案内が来たら時候のあいさつを入れて返信、とか、画面からパスワードを入力して注文、などとやっていたら続かない。紙というものが目の前にあるから何とかしようと思うのだ。本の山を前にして途方に暮れつつ切り崩していくのと同じだ。
未來社のPR誌『未来』の2008年7月号に、リブロの中尾幸葉さんが「紙がみと書店と」と題したエッセイを寄せている。3年勤務した金沢店から持ってきた紙袋がひとつ。中にはシールや絆創膏、出版社とやりとりした紙や売場で拾ったメモが入っている。こういうものをとっておいた中尾さんの人柄が伝わる、静かな名文だ。そう、あふれる紙の山のなかには、宝物もまじっている。
研修旅行2日目はちくさ正文館に行った。名古屋駅で中央線に乗り、千種駅から徒歩3分。思想も文学も芸術も渾然一体となった大きな書斎のような店で、棚の批評をするよりも、黙って本に読みふけってしまう。古本と見まがうような雑誌がそっとささっていたり、倒産した出版社の本が確信犯的に残されていたりするなかで、壁や棚板に貼られた紙たちに目を奪われた。今やっている映画や展覧会の割引券が積んである一方で、だいぶ前に出た本のチラシや、数年前に上演していた演劇のポスターが貼ってある。でも、
「もう終わっているじゃない」
と文句を言う気にはならない。むしろ、この店が当時から今と同じように黙々と本を仕入れ紙を貼ってきたことが感じられて、じんとしてしまう。
詩の棚には「H氏賞受賞」などと書かれた手書きのPOPがいくつか置かれ、その本は近くには見あたらないのだけれど、これもまた
「昔そんなことがあって、大事に売っていたんだろうな」
と納得してしまう。はがし忘れ、捨て忘れには見えないところが、この本屋のすごさだ。
本屋は新しい情報の発信地であるとともに、古いものを捨てずに残しておく場所でもある。古きも新しきも、おなじ紙になって積み重ねられていく。
本は売ればなくなってしまうけれど、周りの紙はとっておける。アーカイブズのような本屋になれたら、全ての本屋がそんなふうになったら、楽しいだろう。
そこで、あるベテラン書店員さんが
「今の店に異動してきて最初にやったのは書類を捨てること。中をちょっとだけ見て、段ボール3箱くらい捨てました。私はもう開けることないな、と思ったので。何でも捨てちゃうんですよ」
と話していて、ああ、ではぜひ私のところにも来て捨ててください! と、口には出さずに思う。店に残してきた、そして今も増えつつある紙の山が頭をよぎる。
本屋には紙があふれている。売っているのは紙の束だ。その周辺にもブックカバーに袋、本に挟まれたスリップ、検定の申込書、チラシ、お客さま用のご注文伝票、出版社からのFAX・・・・・・ と、ペーパーレス化のレの字もない。
出版社の人からフェアの企画書や売上一覧表をどさりと渡されて、とりあえず箱にしまって、そのまま数年が経過する。たまに思いついたようにまとめて捨ててみるけれど、罪悪感がある(出版社の人に、というより、地球に対して)。かといってコンピュータのデータでもらっても絶対に見ない。注文書だって、その場で「5」とか冊数を書き込んで、番線印(書店の住所印のようなもの)をパンと押してFAXするだけだから気楽に返送できるのであって、メールで案内が来たら時候のあいさつを入れて返信、とか、画面からパスワードを入力して注文、などとやっていたら続かない。紙というものが目の前にあるから何とかしようと思うのだ。本の山を前にして途方に暮れつつ切り崩していくのと同じだ。
未來社のPR誌『未来』の2008年7月号に、リブロの中尾幸葉さんが「紙がみと書店と」と題したエッセイを寄せている。3年勤務した金沢店から持ってきた紙袋がひとつ。中にはシールや絆創膏、出版社とやりとりした紙や売場で拾ったメモが入っている。こういうものをとっておいた中尾さんの人柄が伝わる、静かな名文だ。そう、あふれる紙の山のなかには、宝物もまじっている。
研修旅行2日目はちくさ正文館に行った。名古屋駅で中央線に乗り、千種駅から徒歩3分。思想も文学も芸術も渾然一体となった大きな書斎のような店で、棚の批評をするよりも、黙って本に読みふけってしまう。古本と見まがうような雑誌がそっとささっていたり、倒産した出版社の本が確信犯的に残されていたりするなかで、壁や棚板に貼られた紙たちに目を奪われた。今やっている映画や展覧会の割引券が積んである一方で、だいぶ前に出た本のチラシや、数年前に上演していた演劇のポスターが貼ってある。でも、
「もう終わっているじゃない」
と文句を言う気にはならない。むしろ、この店が当時から今と同じように黙々と本を仕入れ紙を貼ってきたことが感じられて、じんとしてしまう。
詩の棚には「H氏賞受賞」などと書かれた手書きのPOPがいくつか置かれ、その本は近くには見あたらないのだけれど、これもまた
「昔そんなことがあって、大事に売っていたんだろうな」
と納得してしまう。はがし忘れ、捨て忘れには見えないところが、この本屋のすごさだ。
本屋は新しい情報の発信地であるとともに、古いものを捨てずに残しておく場所でもある。古きも新しきも、おなじ紙になって積み重ねられていく。
本は売ればなくなってしまうけれど、周りの紙はとっておける。アーカイブズのような本屋になれたら、全ての本屋がそんなふうになったら、楽しいだろう。