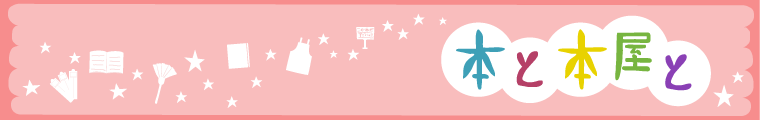本と本屋と
第17回 本屋で触る
大学4年生の秋、万葉集を読む講義をとっていた。あるとき教授が、
「私は手がきれいなんです。自慢ではありません、働いたことのない手ですから、仕方がありません」
と漏らした。言われて目をやる。確かに六十歳を前にした男性のものには見えない、白くてしなやかな手だった。書店で働くことが決まっていた私は、いつも霊魂の恋について語っている先生とは道が分かれたのだと感じた。
次の春から書店の売り子になり、別れの予感の正しさをすぐに悟った。紙をさわると手はおそろしく乾燥する。ハンドクリームは本をべたべたにするのであまり塗れない。手のひらを棚の金具にぶつけて血も流す。爪も割る。注文書はほとんど手書きなのでペンだこが消えない。「職人の手」とはとても呼べないにしても、手作業のあとがあちこちに残っている。
軍手をはめれば解決するだろう。でも、どうも気が進まない。本には素手で触れたい。内容はわからないから、せめて感触を確かめたい。根拠のない感傷かもしれないけれど、他の店員を見てもあまり軍手をしていないのは、実は同じ理由ではないだろうか。
自分が客として書棚の前に立ったときも、気になる本はつい取りだしてしまう。買うつもりがなくても、とりあえず引き抜いてぱらぱらめくって、満足して戻す。活字を目で追う「読書」はしなくても、手にとって開いてみるのも、本との関わりと呼べるだろう。
一方で、本はおびただしい数の手に触れられる。産地直送のスイカとは比べものにならない。製本所から出版社に届けられ、取次に送られ、書店へ入ってきて。下手すると返品されて、取次を通って出版社に戻り、改装されてまた出庫されて、また返品されて、出庫されて。
「君はここが何軒目?」
と聞きたくなるような、疲れはてた本もある。図書館に納品されたりしたら最後、はてしなくたくさんの人の手をまわりつづけることになる。幸せだけど、大変だ。
CDやDVDとちがって、本は鑑賞するあいだ、ずっと手に触れつづけている。どんなに役に立つことが書いてある本でも、手触りが悪ければ読めない。人に譲ってもらった『井伏鱒二選集』(全9巻、筑摩書房、1948 - 49)は、古くて茶色くなった紙がページをめくるたびにぽろぽろとこぼれて、いたたまれない。もう二度と読めないのでは、と心配になる。
『防ぐ技術・治す技術 紙資料保存マニュアル』(日本図書館協会、2005)によると、東京都立中央図書館で所蔵する1940年代の出版物のうち、10冊につき約3冊の本が劣化しているらしい。インクのにじみ止めに硫酸アルミニウムを用いた酸性紙が使われていて、数十年でボロボロになるというのだ。対策としては脱酸性化処理を施す、1980年代以降は本文用紙の中性化が進み、2004年は出版物の90%以上が中性紙を使用している・・・・・・。
読むうちに、ため息が出た。図書館の人はこんなにも本のことを考えているのか。本屋では数十年も同じ本を持っていることなどまずないから、紙質を憂うこともない。ましてや自分で直そうだなんて思いもしない。感触を味わうまえに、数十年後の本を大切にしなければ。『防ぐ技術・治す技術』には、
「本を扱うまえに手を洗いましょう」
とあるので、それくらいは心がけたい。軍手をするように、とは書いていないので、これからも素手で触る。
「私は手がきれいなんです。自慢ではありません、働いたことのない手ですから、仕方がありません」
と漏らした。言われて目をやる。確かに六十歳を前にした男性のものには見えない、白くてしなやかな手だった。書店で働くことが決まっていた私は、いつも霊魂の恋について語っている先生とは道が分かれたのだと感じた。
次の春から書店の売り子になり、別れの予感の正しさをすぐに悟った。紙をさわると手はおそろしく乾燥する。ハンドクリームは本をべたべたにするのであまり塗れない。手のひらを棚の金具にぶつけて血も流す。爪も割る。注文書はほとんど手書きなのでペンだこが消えない。「職人の手」とはとても呼べないにしても、手作業のあとがあちこちに残っている。
軍手をはめれば解決するだろう。でも、どうも気が進まない。本には素手で触れたい。内容はわからないから、せめて感触を確かめたい。根拠のない感傷かもしれないけれど、他の店員を見てもあまり軍手をしていないのは、実は同じ理由ではないだろうか。
自分が客として書棚の前に立ったときも、気になる本はつい取りだしてしまう。買うつもりがなくても、とりあえず引き抜いてぱらぱらめくって、満足して戻す。活字を目で追う「読書」はしなくても、手にとって開いてみるのも、本との関わりと呼べるだろう。
一方で、本はおびただしい数の手に触れられる。産地直送のスイカとは比べものにならない。製本所から出版社に届けられ、取次に送られ、書店へ入ってきて。下手すると返品されて、取次を通って出版社に戻り、改装されてまた出庫されて、また返品されて、出庫されて。
「君はここが何軒目?」
と聞きたくなるような、疲れはてた本もある。図書館に納品されたりしたら最後、はてしなくたくさんの人の手をまわりつづけることになる。幸せだけど、大変だ。
CDやDVDとちがって、本は鑑賞するあいだ、ずっと手に触れつづけている。どんなに役に立つことが書いてある本でも、手触りが悪ければ読めない。人に譲ってもらった『井伏鱒二選集』(全9巻、筑摩書房、1948 - 49)は、古くて茶色くなった紙がページをめくるたびにぽろぽろとこぼれて、いたたまれない。もう二度と読めないのでは、と心配になる。
『防ぐ技術・治す技術 紙資料保存マニュアル』(日本図書館協会、2005)によると、東京都立中央図書館で所蔵する1940年代の出版物のうち、10冊につき約3冊の本が劣化しているらしい。インクのにじみ止めに硫酸アルミニウムを用いた酸性紙が使われていて、数十年でボロボロになるというのだ。対策としては脱酸性化処理を施す、1980年代以降は本文用紙の中性化が進み、2004年は出版物の90%以上が中性紙を使用している・・・・・・。
読むうちに、ため息が出た。図書館の人はこんなにも本のことを考えているのか。本屋では数十年も同じ本を持っていることなどまずないから、紙質を憂うこともない。ましてや自分で直そうだなんて思いもしない。感触を味わうまえに、数十年後の本を大切にしなければ。『防ぐ技術・治す技術』には、
「本を扱うまえに手を洗いましょう」
とあるので、それくらいは心がけたい。軍手をするように、とは書いていないので、これからも素手で触る。