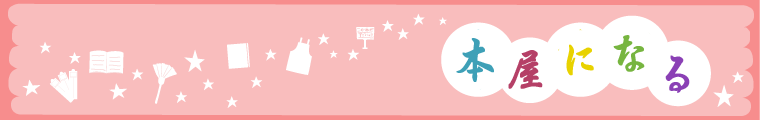本屋になる
第9回 本を捨てる
鈴木地蔵さんの『文士の行蔵』(右文書院)の書き出しに、息をのんだ。
〈島崎藤村は要らない本を海に捨てたそうである。〉
勝本清一郎の『こころの遠近』(朝日新聞社)からの話題である。不要な本がたまると品川沖まで小舟でこいで行き、水葬にしたそうだ。〈海を書物の捨て場所に考案した作家は、日本にも外国にも余り類がなかったであろう。〉
水をふくんでぶよぶよとふくれた本を想像するだけで、心が痛む。ページが海藻に引っかかったり、函と本のあいだに泥がつまったりするのだろう。
あまりのショックに『こころの遠近』を取り寄せてみた。正方形に近い、思いのほかかわいらしいたたずまいの本だった。
「藤村の憶い出」から鈴木さんとは別の箇所を引用してみる。
〈南米の旅からもどってまもなく、先生は私に「帰りの船のなかで少し左翼の方の本を勉強して見ましたよ」といわれた。「読んでしまってから、本はみんな海のなかに捨てて来ました」ともいわれた。なかなか藤村式な話だった。〉
文豪はやることが違う。捨てたら、海のなかのことは考えない。
本を捨てることにとても抵抗があって、たとえただでも古本屋に引き取ってもらえたらと思ってきた。そうすればどうにか有効活用してくれるだろうと。しかし、実際は古本屋こそ本を捨てているのかもしれないと古本屋になってからわかった。
店の整理のために軽トラック2台ぶん処分したとか、どこに持っていくと何キロいくらで買ってもらえるとか。先輩がたの話をきき、長年やっていれば思いきらなければいけないときが出てくるんだなと思った。
このまえ東京古書会館に初めて行った。もらったガイドに「市場で廃棄する本が出たら」という項目があって、また驚いてしまった。市場で他の業者が出品した本を入札して買い、なかにいらない本があると判断したらその場で処分するということだ。持ち帰って調べるまでもなく、この世から消す。売った人もそこにいるのに! シビアすぎる。
古本屋になったはじめは手持ちの本も少なく気も弱くてなにも捨てられなかったけれど、どんどん本がたまり、売れない本はいつまで持っていても売れないとわかり、少しずつ処分するようになった。
一番いいのは、誰かにあげること。店から3分のところに「なんでももらうよ」と言ってくれる古本屋があるので、ときどき持ちこんで引きとってもらう。店頭の3冊100円セールに並べられているのを見るとほっとする。
持っていくのもはばかられる本は、一度だけ資源ごみの日に縛って出した。誰か拾ってくれないかと思ったけれど誰にも拾われず、トラックに運ばれていった。
店をはじめた冬はよく浜辺に出かけて、たき火をして遊んでいた。段ボールや廃材を燃やし、足りなくなると森に入っていって燃やせるものを探すのだが、意外といいものが見つからない。なにか目新しい薪がないだろうかと思っていた。
ある日お客さんが本をくれて、中に古い文芸書が数冊まじっていた。カバーがなく、カビがはえていたり水に濡れていたり、初心者の私にも「これは売りものにならない」とはっきりわかる本だった。そうだ、今夜はこれを燃やしてみよう。火葬はごく伝統的な本の処分法だから。
いつものように段ボールからはじめる。
「これも燃やしていい」
取りだすと、ぎょっとされた。
1ページちぎって投げこむ。じりじりと端のほうから波うちながら燃えて、真っ黒でいびつなかたまりになった。汚らしい。ぱっと灰になるのかと思っていた。
1ページ、また1ページ。面倒になってひとつかみ放り投げると、外側のページだけがへなへなと燃え、中のページには火がうつらない。また破りなおす。
こんなに手がかかるとは知らなかった。よく漫画で古い手紙や日記を燃やす場面があったけれど、投げこめばはらはらと調子よく燃えあがっていたような気がする。あるいは華氏451度に達していないのだろうか。あれは燃やすまえに石油に浸すのだったか。
「それ、どうしても燃やさなきゃいけないの?」
いらいらしている私を見かねたように、声がかかる。
「いらないもん」
「ちょっと見せてよ」
まだ手つかずの2冊を手渡す。
「面白そうじゃない。読むから、ちょうだい」
「いいよ」
1冊は人の手にわたった。
「そっちも見せて」
もうひとりが残った1冊をつかんだ。
「もらってもいい」
「どうぞ」
焚書はまぬがれた。
東京古書会館で唯一落札できた束に、『古本屋 月の輪書林』(高橋徹、晶文社)が入っていた。目録作りを通して本に新しい価値をつけていくという、ただ本を入れて売るだけの古本屋とはまったく違う仕事をされている方の本である。日録のなかにたとえば「五反田入札市の落札品が届く。まるで“ゴミの山”である」という書き方が出てくる。
『彷書月刊編集長』(田村治芳、晶文社)も同じ束に入っていた。こちらには「頭のスミで、もうひとりのわたしの『ちっ、ゴミだな』という声が聞こえてきても、『そうだよ。でも、ゴミだからおもしろいんじゃないか』というわたしの声も聞こえてくるのです」という一節があった。
みんなが欲しがるものを欲しがっても勝てるわけがない。ゴミを見てゴミだと言いたいところをぐっとおさえてなにかを見つけるのが古本屋の勝負なのだ。
自分でおもしろさを見つけられないからといって1冊の本をこの世から抹消してしまうわけにはいかないか、とも思えてくる。捨てたさと捨てられなさが、いつもせめぎあっている。
〈島崎藤村は要らない本を海に捨てたそうである。〉
勝本清一郎の『こころの遠近』(朝日新聞社)からの話題である。不要な本がたまると品川沖まで小舟でこいで行き、水葬にしたそうだ。〈海を書物の捨て場所に考案した作家は、日本にも外国にも余り類がなかったであろう。〉
水をふくんでぶよぶよとふくれた本を想像するだけで、心が痛む。ページが海藻に引っかかったり、函と本のあいだに泥がつまったりするのだろう。
あまりのショックに『こころの遠近』を取り寄せてみた。正方形に近い、思いのほかかわいらしいたたずまいの本だった。
「藤村の憶い出」から鈴木さんとは別の箇所を引用してみる。
〈南米の旅からもどってまもなく、先生は私に「帰りの船のなかで少し左翼の方の本を勉強して見ましたよ」といわれた。「読んでしまってから、本はみんな海のなかに捨てて来ました」ともいわれた。なかなか藤村式な話だった。〉
文豪はやることが違う。捨てたら、海のなかのことは考えない。
本を捨てることにとても抵抗があって、たとえただでも古本屋に引き取ってもらえたらと思ってきた。そうすればどうにか有効活用してくれるだろうと。しかし、実際は古本屋こそ本を捨てているのかもしれないと古本屋になってからわかった。
店の整理のために軽トラック2台ぶん処分したとか、どこに持っていくと何キロいくらで買ってもらえるとか。先輩がたの話をきき、長年やっていれば思いきらなければいけないときが出てくるんだなと思った。
このまえ東京古書会館に初めて行った。もらったガイドに「市場で廃棄する本が出たら」という項目があって、また驚いてしまった。市場で他の業者が出品した本を入札して買い、なかにいらない本があると判断したらその場で処分するということだ。持ち帰って調べるまでもなく、この世から消す。売った人もそこにいるのに! シビアすぎる。
古本屋になったはじめは手持ちの本も少なく気も弱くてなにも捨てられなかったけれど、どんどん本がたまり、売れない本はいつまで持っていても売れないとわかり、少しずつ処分するようになった。
一番いいのは、誰かにあげること。店から3分のところに「なんでももらうよ」と言ってくれる古本屋があるので、ときどき持ちこんで引きとってもらう。店頭の3冊100円セールに並べられているのを見るとほっとする。
持っていくのもはばかられる本は、一度だけ資源ごみの日に縛って出した。誰か拾ってくれないかと思ったけれど誰にも拾われず、トラックに運ばれていった。
店をはじめた冬はよく浜辺に出かけて、たき火をして遊んでいた。段ボールや廃材を燃やし、足りなくなると森に入っていって燃やせるものを探すのだが、意外といいものが見つからない。なにか目新しい薪がないだろうかと思っていた。
ある日お客さんが本をくれて、中に古い文芸書が数冊まじっていた。カバーがなく、カビがはえていたり水に濡れていたり、初心者の私にも「これは売りものにならない」とはっきりわかる本だった。そうだ、今夜はこれを燃やしてみよう。火葬はごく伝統的な本の処分法だから。
いつものように段ボールからはじめる。
「これも燃やしていい」
取りだすと、ぎょっとされた。
1ページちぎって投げこむ。じりじりと端のほうから波うちながら燃えて、真っ黒でいびつなかたまりになった。汚らしい。ぱっと灰になるのかと思っていた。
1ページ、また1ページ。面倒になってひとつかみ放り投げると、外側のページだけがへなへなと燃え、中のページには火がうつらない。また破りなおす。
こんなに手がかかるとは知らなかった。よく漫画で古い手紙や日記を燃やす場面があったけれど、投げこめばはらはらと調子よく燃えあがっていたような気がする。あるいは華氏451度に達していないのだろうか。あれは燃やすまえに石油に浸すのだったか。
「それ、どうしても燃やさなきゃいけないの?」
いらいらしている私を見かねたように、声がかかる。
「いらないもん」
「ちょっと見せてよ」
まだ手つかずの2冊を手渡す。
「面白そうじゃない。読むから、ちょうだい」
「いいよ」
1冊は人の手にわたった。
「そっちも見せて」
もうひとりが残った1冊をつかんだ。
「もらってもいい」
「どうぞ」
焚書はまぬがれた。
東京古書会館で唯一落札できた束に、『古本屋 月の輪書林』(高橋徹、晶文社)が入っていた。目録作りを通して本に新しい価値をつけていくという、ただ本を入れて売るだけの古本屋とはまったく違う仕事をされている方の本である。日録のなかにたとえば「五反田入札市の落札品が届く。まるで“ゴミの山”である」という書き方が出てくる。
『彷書月刊編集長』(田村治芳、晶文社)も同じ束に入っていた。こちらには「頭のスミで、もうひとりのわたしの『ちっ、ゴミだな』という声が聞こえてきても、『そうだよ。でも、ゴミだからおもしろいんじゃないか』というわたしの声も聞こえてくるのです」という一節があった。
みんなが欲しがるものを欲しがっても勝てるわけがない。ゴミを見てゴミだと言いたいところをぐっとおさえてなにかを見つけるのが古本屋の勝負なのだ。
自分でおもしろさを見つけられないからといって1冊の本をこの世から抹消してしまうわけにはいかないか、とも思えてくる。捨てたさと捨てられなさが、いつもせめぎあっている。