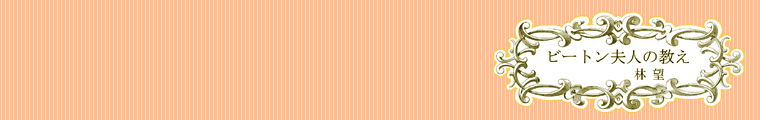ビートン夫人の教え
4 <後編>
第二章「ハウスキーパー」
現代では、ふつうの家庭にハウスキーパーやら料理人やらを雇うということはなくなったので、この章に書かれていることはほとんど意味がなくなってしまったかに見える。しかし、そのなかでも、ハウスキーパーの四季折々の仕事について概述しているところは、今に変わらぬイギリス人の暮らしぶりを彷彿させるところがあるので、その要点を紹介しておくことにしたい。
ハウスキーパー(敢て訳せば「女中頭」)という存在は、一家の女性たちのなかで女主人に次ぐ地位を占めるもので、その統括下に下働きのメイドなどがいるわけである。
概して、当時の住宅にあっては、冬の間は暖炉の始末やら掃除やら、火の世話の仕事が多く、ルーティンの仕事以外のことまではあまり手が回らなかったらしい。しかし、夏になると、火の回りの仕事がない分、ほかのあれこれのことができるというわけで、ビートン夫人は四季の仕事の概要を次のように纏めている。
「春は大掃除にもってこいの季節である。冬期は、どんなに掃除に努めても、石炭、ガス、燃料オイルから出る煙や煤で汚れがたまってしまうものだから。この季節はまた、普段は洗わないような、重く大きなリネン類や毛布などの洗濯や漂白をすべき季節である。こういう仕事は七月ころにせよと勧めるむきもあるけれど、なにぶんこうした大物を扱うのは力仕事で、暑い時季には汗をかくため、むしろ春にやるほうがよい。
冬のカーテンは外して、夏用の白いものに掛け替える。また毛皮やウールはハンガーから下ろして注意深く横に寝かせる。冬用のカーテンは、外したらよく振るってブラシをかけ、虫よけに樟脳を紙か布に包んでピンで留めておくとよい。毛皮も同様。
一般に家の大掃除という場合には、抽斗(ひきだし)や戸棚、物置、天井裏、その他すみずみまで清掃することが含まれるので、そういうところに不要なものを溜めておくことが、やがてはゴミとなり、また害虫発生のもとともなることを理解しておくべきである。なおかつ、煙突を掃除し、カーペットを剥いで清掃し、台所やオフィスの漆喰を塗り替えたりペンキを塗ったり、あるいは必要とあらば部屋の壁紙を張り替えたり、来たるべき夏に備えて、おおむね、家の内外を明るくし、自然に同調しつつリフレッシュするとよい。
またこの時期にオレンジのマーマレードや、オレンジワインなどを作る」
こういう記述を読むにつけて、イギリスの長くて暗い冬を思い出す。日本と違って、イギリスの冬は、ともかく日照時間が短くて真っ暗である。それがために「冬鬱病」という病気があるくらいなのだ。しかも、冬が雨季であるといってもよろしく、イギリスの冬はじめじめと冷雨が降って骨身に応える嫌な寒さである。それだけに、冬がしさって春が来た時の、ある輝かしい思い、その爆発的な嬉しさは、日本にいてはちょっと想像のほかかもしれない。
だからこそ、ビートン夫人は、春にこういうさまざまの掃除や手入れをせよと教えているのである。
次に、夏。夏にはリネン類のチェックや、その手入れの仕方を概述したあとで、さまざまの食べ物について言及している。
「六月と七月には、グーズベリー(セイヨウスグリ)や、カラント(スグリ)、ラズベリー(キイチゴ)、イチゴ、その他、夏の果物の保存食品を作り、またジャムやジェリー(訳注、これは日本人が一般的に思い浮かべるゼリーではなくて、潰した実を漉してジュースにし、それを煮詰めて作る果肉の入らないジャムという形のもの)を作る。また七月には、クルミの木になっているクルミのまだ青い実がクルミのケチャップ(訳注、ケチャップというものは、中国語の「茄汁」から出た言葉だともいうのだが、野菜を煮詰めて作る調味料を一般に言い、材料はトマトに限らない。ほかにマッシュルームのケチャップなども知られている)を作るのにちょうど良い頃なので、作ってみるとよい。あるいは、ミックスピクルスを作るのにも好適な季節である。ピクルス汁(作り方は後述)を作って瓶に入れておくと便利である。この汁の中に、フレンチビーンやカリフラワーなどを漬けることなどもある」
じっさい、夏になると、サマープディングというデザートが食卓に供せられるのがイギリスの風習である。これは、食パンの中に、カラントやチェリーやラズベリーや、さまざまの赤い夏の果実を煮たものを入れて、たっぷりの煮汁をしみ込ませ、冷蔵庫で一晩冷やし固めたもので、食卓で切り分けて生クリームをかけて食べる。じつに美しくまたおいしいものであるが、イギリスはベリー類の宝庫で、それらはいずれも夏にいっせいに熟すので、サマープディングなどが季節の風物詩として愉しまれるわけである。
クルミのケチャップの作り方は、この本には何故か書いていないのであるが、ただ青クルミのピクルスについてはレセピがある。日本では、クルミといえば、あの種の中子(なかご)のみを食べて、木に成っている青い果実の状態では手に入らないので、作ってみることは難しいけれど、おそらくはその青い果肉を煮て、塩とスパイスで味を付け、裏ごしでもしてドロリとしたペースト状に作るものかと想像される。それもなんだかおいしそうな感じがする。
さらに、
「初秋のころには、各種のプラムを瓶詰めにしたり、ジャムやジェリーにして保存する。またその少し後には、作っておくと大変便利なトマトソースなども自作して保存しておくとよい。
またもし適当な場所があるならば、リンゴを並べて置くのもよろしく、梨やハシバミ(fibbert)を保存しておく人もある。さらには大きな野菜類、たとえばペポカボチャ(marrow、訳注、黄色い瓜のような格好の野菜で、中身は冬瓜にやや似る)の保存を試みてみてはどうか。冬まで保存して食べると大変に美味しいものである」
とある。このリンゴや梨やハシバミを並べておくというのは、どういうことかというと、こうした果実は枝から取ってきた当座は堅くて甘味も香りも充分でない。しかし、これを冷暗所に保存しておくとしばらくするうちに完熟して甘く香り高くなる。イギリスではそういうふうにしてこれらの果実を愉しむことは、今でも普通におこなわれているのである。
「十月、十一月になったら、来たるべき寒い冬に備えて家族全員の冬服を準備する。夏の白いカーテンは外して丁寧にしまうようにしたい。また暖炉や火格子(grates、訳注、暖炉の前のほうにある鉄製の格子で、その上に薪を置いて燃やす床)、さらには煙突の準備をし、家のあちこちをきちんと修理して、あとになってとんだ不愉快な思いをしたり、また余分な修理費の出費を余儀なくされたりということがないように備えたい。
十二月には、家事のなかでももっとも主要な仕事として身近な親しい人たちのお楽しみの準備ということがある。つまり、クリスマスを、みんなが笑顔で、満ち足りた気持ちで迎えられるように、そうして、食品庫に食べ物を一杯に満たし、プラムの種を抜き、スグリを洗い、シトロン(訳注、菓子の香り付けなどにつかう柑橘類)を刻み、卵を割りほぐし、そうして『プディングを混ぜる』。主婦にとって、楽しいことばかりのこのなごやかなひとときを祝うことは決して意味のないことではない」
と、このようにビートン夫人は筆を揮っているのであるが、十月から十一月という季節は、イギリス人にとってはもっとも憂鬱な季節であると言って過言でない。
楽しかった夏も過ぎ、美しい秋も老いて、いまや暗く冷たくじめじめと暗鬱な冬が、目前に迫ってくる。日々に日脚は驚くほど短くなって、毎日雨ばかりビショビショと降る。そういう季節である。そういう暗澹たる思いを抱えながら、しかし、せめて冬が寒くないように、暖炉やカーテンの準備をせよというのである。
しかし十二月は、一年のうちでもっとも嬉しい祝祭ともいうべきクリスマスがやって来る。イギリスのクリスマスは、気分的には日本のお正月に近い。
そうして、ここに書かれている、「プラムの種を抜き」以下の記述は、すべて、例のクリスマス・プディングの準備にほかならない。
クリスマス・プディングは、膨大な量の干し果実と、牛の脂と、少量の小麦粉と、そして卵と、砂糖と、さまざまのスパイスを、大きな鉢などに入れて、家族こぞって代わる代わる木の箆を執って混ぜあわせて作るのである。これは言ってみれば日本のお餅搗きみたいな祝祭的営為なのであって、ビートン夫人はこのところ、とくに「MIXING THE PUDDING」と大文字で特記しているのである。
第三章 台所のアレンジと経済性
ここではビートン夫人は、主婦やハウスキーパーらにとっての主要な働き場所であるところの台所について、あれこれと歴史的考察やら現代の道具類やら、しごく具体的に述べていて、これらはおのずから、ヴィクトリア時代における、台所の意味や理想を論ずるところとなっている。
まず夫人は、高名なる哲学者にして内科医でもあったラムフォード伯爵の「台所の配置は・・・原則として、どんな場合にもシンプルで分かりやすく作られるべきである」という言説をまず紹介して、しかし、もう少し特別の注意が払われるべきことを述べる。
なぜなら、この台所という空間の内部で、身体の健康に関するすべてが作られるからだというのである。
「従って、良い台所とは、次のような事共にとくに注意して作らなくてはならない」として、五つの条件を列記する。
ただし、第四項の、住居部分から充分に距離があって調理の匂いが居間などに伝わらないこと、というのは、規模の小さな家においては充分満たされないこともあったが、それでも、多くはたしかに居間部分と台所とは階層を異にするというような配慮が認められた。
しかし、私の見た所では、イギリスの台所は、家のなかのもっとも見晴らしのよいところに設けられていることが多かった。これは、上記の第一項にも関係していることと思われるが、台所が半地下のようなところにあって、もっぱら使用人たちが黙々とそこで働いていたヴィクトリア時代以前の富豪や貴族の家のような場合とは事変り、家の主婦が自ら調理やその監督に当たるヴィクトリア時代以降の中産階級の家々にあっては、台所がさような陰鬱な場所であってはいけなかったということでもあろう。自ら台所で大いに調理に当たったビートン夫人自身が、誰よりも台所の近代化に熱心であったということは当然であって、彼女のこうした唱道が、その後のイギリスの住宅設計に与えた影響も決して過少に見積もってはいけない。
私は、かつてエドワーディアンの美しい住宅に住むイギリス人W夫人にこう訊ねたことがある。
「どうしてイギリスの台所はこういう景色の良い場所に設けてあるのですか」
すると、彼女は、その美しく整備されたガーデンを正面見る明るい台所に視線を放ちながら、こう言った。
「だってね、台所の仕事ってものは、食器を洗ったり、たべものの下ごしらえをしたり、まあ退屈で単調なことも多いでしょう。だから、せめてこういう美しい景色を眺めながら、楽しく家事が出来るようにするのが、イギリスの主婦の智慧というわけですよ」
こういう思念の中にも、あの十九世紀のイザベラ・ビートン夫人の心意気がいくらかは反映しているのに違いないと私は思うのである。
現代では、ふつうの家庭にハウスキーパーやら料理人やらを雇うということはなくなったので、この章に書かれていることはほとんど意味がなくなってしまったかに見える。しかし、そのなかでも、ハウスキーパーの四季折々の仕事について概述しているところは、今に変わらぬイギリス人の暮らしぶりを彷彿させるところがあるので、その要点を紹介しておくことにしたい。
ハウスキーパー(敢て訳せば「女中頭」)という存在は、一家の女性たちのなかで女主人に次ぐ地位を占めるもので、その統括下に下働きのメイドなどがいるわけである。
概して、当時の住宅にあっては、冬の間は暖炉の始末やら掃除やら、火の世話の仕事が多く、ルーティンの仕事以外のことまではあまり手が回らなかったらしい。しかし、夏になると、火の回りの仕事がない分、ほかのあれこれのことができるというわけで、ビートン夫人は四季の仕事の概要を次のように纏めている。
「春は大掃除にもってこいの季節である。冬期は、どんなに掃除に努めても、石炭、ガス、燃料オイルから出る煙や煤で汚れがたまってしまうものだから。この季節はまた、普段は洗わないような、重く大きなリネン類や毛布などの洗濯や漂白をすべき季節である。こういう仕事は七月ころにせよと勧めるむきもあるけれど、なにぶんこうした大物を扱うのは力仕事で、暑い時季には汗をかくため、むしろ春にやるほうがよい。
冬のカーテンは外して、夏用の白いものに掛け替える。また毛皮やウールはハンガーから下ろして注意深く横に寝かせる。冬用のカーテンは、外したらよく振るってブラシをかけ、虫よけに樟脳を紙か布に包んでピンで留めておくとよい。毛皮も同様。
一般に家の大掃除という場合には、抽斗(ひきだし)や戸棚、物置、天井裏、その他すみずみまで清掃することが含まれるので、そういうところに不要なものを溜めておくことが、やがてはゴミとなり、また害虫発生のもとともなることを理解しておくべきである。なおかつ、煙突を掃除し、カーペットを剥いで清掃し、台所やオフィスの漆喰を塗り替えたりペンキを塗ったり、あるいは必要とあらば部屋の壁紙を張り替えたり、来たるべき夏に備えて、おおむね、家の内外を明るくし、自然に同調しつつリフレッシュするとよい。
またこの時期にオレンジのマーマレードや、オレンジワインなどを作る」
こういう記述を読むにつけて、イギリスの長くて暗い冬を思い出す。日本と違って、イギリスの冬は、ともかく日照時間が短くて真っ暗である。それがために「冬鬱病」という病気があるくらいなのだ。しかも、冬が雨季であるといってもよろしく、イギリスの冬はじめじめと冷雨が降って骨身に応える嫌な寒さである。それだけに、冬がしさって春が来た時の、ある輝かしい思い、その爆発的な嬉しさは、日本にいてはちょっと想像のほかかもしれない。
だからこそ、ビートン夫人は、春にこういうさまざまの掃除や手入れをせよと教えているのである。
次に、夏。夏にはリネン類のチェックや、その手入れの仕方を概述したあとで、さまざまの食べ物について言及している。
「六月と七月には、グーズベリー(セイヨウスグリ)や、カラント(スグリ)、ラズベリー(キイチゴ)、イチゴ、その他、夏の果物の保存食品を作り、またジャムやジェリー(訳注、これは日本人が一般的に思い浮かべるゼリーではなくて、潰した実を漉してジュースにし、それを煮詰めて作る果肉の入らないジャムという形のもの)を作る。また七月には、クルミの木になっているクルミのまだ青い実がクルミのケチャップ(訳注、ケチャップというものは、中国語の「茄汁」から出た言葉だともいうのだが、野菜を煮詰めて作る調味料を一般に言い、材料はトマトに限らない。ほかにマッシュルームのケチャップなども知られている)を作るのにちょうど良い頃なので、作ってみるとよい。あるいは、ミックスピクルスを作るのにも好適な季節である。ピクルス汁(作り方は後述)を作って瓶に入れておくと便利である。この汁の中に、フレンチビーンやカリフラワーなどを漬けることなどもある」
じっさい、夏になると、サマープディングというデザートが食卓に供せられるのがイギリスの風習である。これは、食パンの中に、カラントやチェリーやラズベリーや、さまざまの赤い夏の果実を煮たものを入れて、たっぷりの煮汁をしみ込ませ、冷蔵庫で一晩冷やし固めたもので、食卓で切り分けて生クリームをかけて食べる。じつに美しくまたおいしいものであるが、イギリスはベリー類の宝庫で、それらはいずれも夏にいっせいに熟すので、サマープディングなどが季節の風物詩として愉しまれるわけである。
クルミのケチャップの作り方は、この本には何故か書いていないのであるが、ただ青クルミのピクルスについてはレセピがある。日本では、クルミといえば、あの種の中子(なかご)のみを食べて、木に成っている青い果実の状態では手に入らないので、作ってみることは難しいけれど、おそらくはその青い果肉を煮て、塩とスパイスで味を付け、裏ごしでもしてドロリとしたペースト状に作るものかと想像される。それもなんだかおいしそうな感じがする。
さらに、
「初秋のころには、各種のプラムを瓶詰めにしたり、ジャムやジェリーにして保存する。またその少し後には、作っておくと大変便利なトマトソースなども自作して保存しておくとよい。
またもし適当な場所があるならば、リンゴを並べて置くのもよろしく、梨やハシバミ(fibbert)を保存しておく人もある。さらには大きな野菜類、たとえばペポカボチャ(marrow、訳注、黄色い瓜のような格好の野菜で、中身は冬瓜にやや似る)の保存を試みてみてはどうか。冬まで保存して食べると大変に美味しいものである」
とある。このリンゴや梨やハシバミを並べておくというのは、どういうことかというと、こうした果実は枝から取ってきた当座は堅くて甘味も香りも充分でない。しかし、これを冷暗所に保存しておくとしばらくするうちに完熟して甘く香り高くなる。イギリスではそういうふうにしてこれらの果実を愉しむことは、今でも普通におこなわれているのである。
「十月、十一月になったら、来たるべき寒い冬に備えて家族全員の冬服を準備する。夏の白いカーテンは外して丁寧にしまうようにしたい。また暖炉や火格子(grates、訳注、暖炉の前のほうにある鉄製の格子で、その上に薪を置いて燃やす床)、さらには煙突の準備をし、家のあちこちをきちんと修理して、あとになってとんだ不愉快な思いをしたり、また余分な修理費の出費を余儀なくされたりということがないように備えたい。
十二月には、家事のなかでももっとも主要な仕事として身近な親しい人たちのお楽しみの準備ということがある。つまり、クリスマスを、みんなが笑顔で、満ち足りた気持ちで迎えられるように、そうして、食品庫に食べ物を一杯に満たし、プラムの種を抜き、スグリを洗い、シトロン(訳注、菓子の香り付けなどにつかう柑橘類)を刻み、卵を割りほぐし、そうして『プディングを混ぜる』。主婦にとって、楽しいことばかりのこのなごやかなひとときを祝うことは決して意味のないことではない」
と、このようにビートン夫人は筆を揮っているのであるが、十月から十一月という季節は、イギリス人にとってはもっとも憂鬱な季節であると言って過言でない。
楽しかった夏も過ぎ、美しい秋も老いて、いまや暗く冷たくじめじめと暗鬱な冬が、目前に迫ってくる。日々に日脚は驚くほど短くなって、毎日雨ばかりビショビショと降る。そういう季節である。そういう暗澹たる思いを抱えながら、しかし、せめて冬が寒くないように、暖炉やカーテンの準備をせよというのである。
しかし十二月は、一年のうちでもっとも嬉しい祝祭ともいうべきクリスマスがやって来る。イギリスのクリスマスは、気分的には日本のお正月に近い。
そうして、ここに書かれている、「プラムの種を抜き」以下の記述は、すべて、例のクリスマス・プディングの準備にほかならない。
クリスマス・プディングは、膨大な量の干し果実と、牛の脂と、少量の小麦粉と、そして卵と、砂糖と、さまざまのスパイスを、大きな鉢などに入れて、家族こぞって代わる代わる木の箆を執って混ぜあわせて作るのである。これは言ってみれば日本のお餅搗きみたいな祝祭的営為なのであって、ビートン夫人はこのところ、とくに「MIXING THE PUDDING」と大文字で特記しているのである。
第三章 台所のアレンジと経済性
ここではビートン夫人は、主婦やハウスキーパーらにとっての主要な働き場所であるところの台所について、あれこれと歴史的考察やら現代の道具類やら、しごく具体的に述べていて、これらはおのずから、ヴィクトリア時代における、台所の意味や理想を論ずるところとなっている。
まず夫人は、高名なる哲学者にして内科医でもあったラムフォード伯爵の「台所の配置は・・・原則として、どんな場合にもシンプルで分かりやすく作られるべきである」という言説をまず紹介して、しかし、もう少し特別の注意が払われるべきことを述べる。
なぜなら、この台所という空間の内部で、身体の健康に関するすべてが作られるからだというのである。
「従って、良い台所とは、次のような事共にとくに注意して作らなくてはならない」として、五つの条件を列記する。
- 一、
- 各部分が、台所の規模の大小に対して便利に配置されていること。
- 二、
- 採光充分に、天井高く、また換気が良いこと。
- 三、
- 家の中を通り抜けることなく、容易に出入出来ること。
- 四、
- 家の主要な住居部分から充分な距離があって、家族や訪問者あるいは来客に調理の匂いが伝わらないこと。
- 五、
- 燃料や水が豊富で、洗い場(scullery、訳注、台所に隣接して、庭から取ってきた野菜を洗ったり、鶏などの毛を毟ったりする場所)やパントリー(食器や食品を保存しておく部屋)、あるいは物置に近接していて、それらとの行き来が容易であること。
ただし、第四項の、住居部分から充分に距離があって調理の匂いが居間などに伝わらないこと、というのは、規模の小さな家においては充分満たされないこともあったが、それでも、多くはたしかに居間部分と台所とは階層を異にするというような配慮が認められた。
しかし、私の見た所では、イギリスの台所は、家のなかのもっとも見晴らしのよいところに設けられていることが多かった。これは、上記の第一項にも関係していることと思われるが、台所が半地下のようなところにあって、もっぱら使用人たちが黙々とそこで働いていたヴィクトリア時代以前の富豪や貴族の家のような場合とは事変り、家の主婦が自ら調理やその監督に当たるヴィクトリア時代以降の中産階級の家々にあっては、台所がさような陰鬱な場所であってはいけなかったということでもあろう。自ら台所で大いに調理に当たったビートン夫人自身が、誰よりも台所の近代化に熱心であったということは当然であって、彼女のこうした唱道が、その後のイギリスの住宅設計に与えた影響も決して過少に見積もってはいけない。
私は、かつてエドワーディアンの美しい住宅に住むイギリス人W夫人にこう訊ねたことがある。
「どうしてイギリスの台所はこういう景色の良い場所に設けてあるのですか」
すると、彼女は、その美しく整備されたガーデンを正面見る明るい台所に視線を放ちながら、こう言った。
「だってね、台所の仕事ってものは、食器を洗ったり、たべものの下ごしらえをしたり、まあ退屈で単調なことも多いでしょう。だから、せめてこういう美しい景色を眺めながら、楽しく家事が出来るようにするのが、イギリスの主婦の智慧というわけですよ」
こういう思念の中にも、あの十九世紀のイザベラ・ビートン夫人の心意気がいくらかは反映しているのに違いないと私は思うのである。